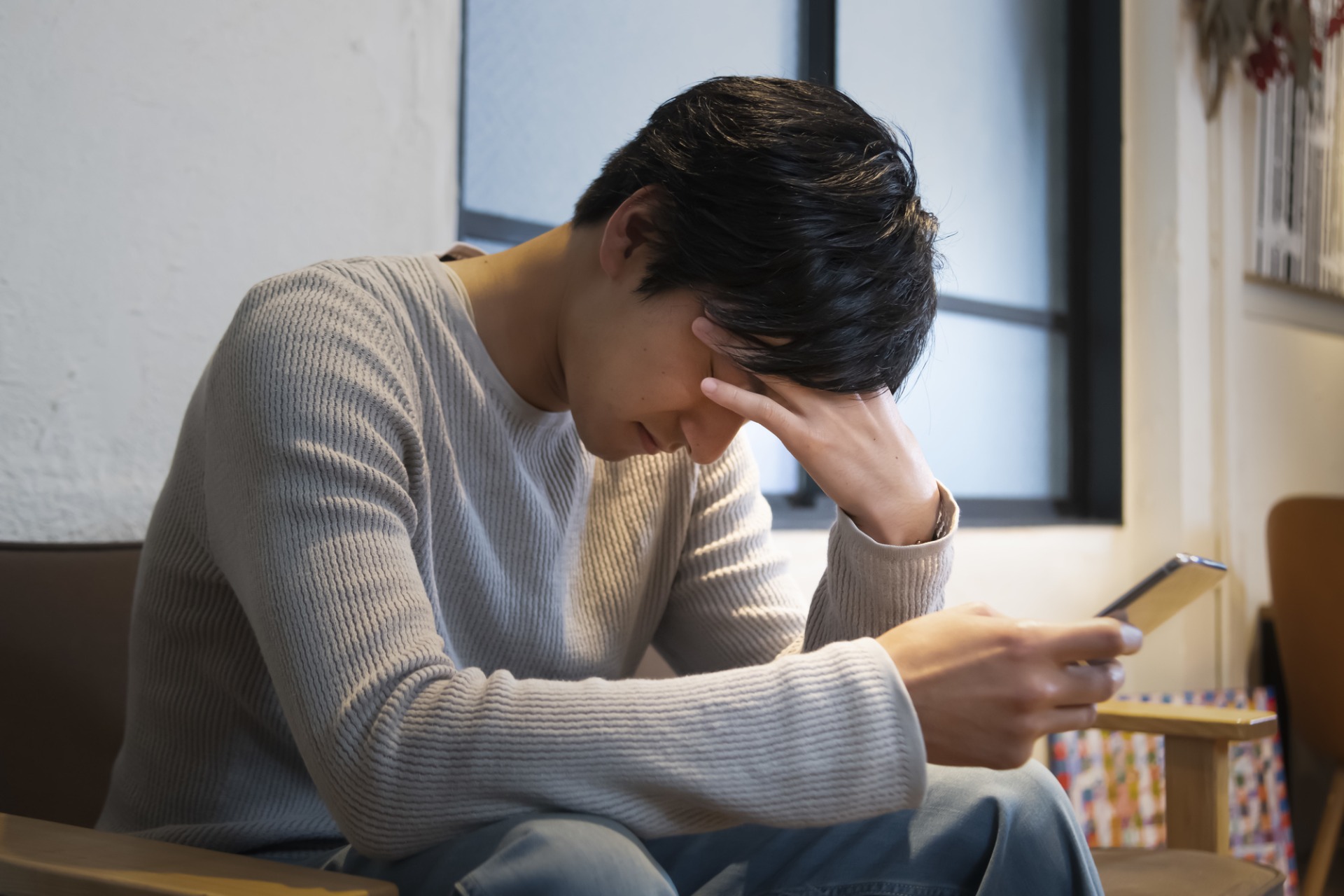デジタルデバイド(情報格差)とは?意味や問題点・解決策を簡単に解説

デジタルデバイドとは、自治体や国、はたまた個人間で生まれる情報格差のことです。デジタルデバイドが起きることでどんな問題が起きるのか、そもそも原因は何かを紹介していきます。あわせて、デジタルデバイドを減らすための企業・自治体の解決策について解説していくので参考にしてみてください。

監修者 福本大一 株式会社kubellパートナー アシスタント事業本部|ユニット長 大学卒業後、toC領域のWEBメディア事業で起業。事業グロースに向けたSEO戦略から営業・運用広告に従事し、約2年間の経営を経て事業譲渡。2021年3月からChatwork株式会社(現:株式会社kubell)に入社し、カスタマーマーケティングやアライアンスを経験した後、メディア事業・運用広告事業の責任者としてミッションを遂行する。現在は、DXソリューション推進部のマネージャーとして新規事業領域のセールス・マーケティング・アライアンス・メディア事業を統括。
目次
デジタルデバイドの意味
デジタルデバイドとは「インターネットやコンピューターなどの利用やそれらを用いたSNSの活用ができる人と、そうではない人の間に生まれる情報格差」のことをいいます。
近年、インターネットの普及により、私たちはスマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスを日常的に利用するようになりました。
その一方で、これらのデジタル化について行けずに取り残されている「情報的弱者」も存在しており、このような「デジタルデバイド」が問題視されるようになりました。
▷デジタル化の意味とは?定義や必要性が高まる背景・推進方法を徹底解説
日本のデジタルデバイドの現状
総務省による令和3年度の通信利用動向調査によると、日本における人口(6歳以上)の82.9%がインターネットを利用しています。
しかし、60歳以上では年齢層の上昇に反比例してインターネット利用率は下がる傾向にあり、70代のインターネット利用率は59.4%、80代になるとと27,6%となっています。
加えて、SNSの利用状況も20代が最も多く、年代が上がるにつれて利用率は低くなっているのが現状となっているのです。
[出典:総務省「令和2通信利用動向調査の結果」]
デジタルデバイドの具体例
まずはデジタルデバイドとして具体的にどのようなケースが挙げられるのかを見ていきます。
会社で起こりやすいデジタルデバイドの具体例
会社で発生しやすいデジタルデバイドとして、年齢や学歴の違いによるITに対しての知識量の差が挙げられます。
ITリテラシーが十分に習得されていないことが原因となり、セキュリティ面のトラブルやIT機器の取り扱いが困難になるなど、業務に支障が出るケースが想定されます。
新しいシステムやツールを導入しても、社内で問題なく利用できる人・上手く利用できない人に分かれてしまい、全社的なデジタル化の推進ができないことが問題となっているのです。
自治体・地域で起こるデジタルデバイドの具体例
自治体や地域で生じるデジタルデバイドとして、インフラ整備の格差が挙げられます。
近年では、都市部と地方間における「5G回線」の普及に差が出ています。都市部では現在もなお5G回線に対応したエリアの拡大が進んでいますが、地方では基地局整備の差が進んでおらず、今もなお広いエリアで5G回線は未対応となっています。
このような各自治体や地域によるインターネット環境の格差は、ビジネスへの影響も危惧されています。
国際的に起こるデジタルデバイドの具体例
国際的に生じるデジタルデバイドとして、先進国と発展途上国の国家間における情報格差が挙げられます。
先進国と発展途上国の違いは、インフラ整備や国家予算だけでなく、それぞれの国家間における教育の差が原因となる格差も存在します。
また、近年はビジネスにおいてもグローバル化が進んでおり、多国籍企業や外国企業などの買収が散見されるようになりました。
しかし一方では、国によってインターネットを利用した情報統制や検閲の実施が原因となり、スムーズなビジネス展開ができない国も見られます。
▷デジタルデバイド解消の取り組みとは?企業や自治体が実施すべき理由や対策
デジタルデバイドが引き起こす問題
デジタルデバイドは、個人間だけではなくさまざまな場面で起こりうる可能性があります。ここでは、デジタルデバイドが引き起こす6つの問題について解説します。
- デジタルに親和性がない世代が孤立する
- 所得に大きな差が生まれやすい
- DX化が進まず生産性が落ちる
- 企業セキュリティの低下リスクがある
- デジタルデバイドを利用した詐欺や事件が起こる
- 技術や人材が流出してしまう
(1)デジタルに親和性がない世代が孤立する
デジタルデバイドは、企業におけるデジタルに親和性がない世代の孤立を引き起こします。
近年、PCやITツールの活用は業務において必要不可欠となりましたが、これらのデジタルツールをうまく活用できない世代は、業務に支障が出てしまうため、結果として孤立する可能性があります。
社員の年齢格差が激しく高齢の社員が多い企業では特に問題となります。社員によってツールやサービスが利用できないなどの問題が発生し、業務が属人化してしまいます。
(2)所得に大きな差が生まれやすい
デジタルデバイドは、所得格差を引き起こします。近年はビジネスの多様化により、実店舗を持たずにインターネット上で全てが完結する事業が増加しています。
このため、ITスキルに長けている人ほど就職しやすく、そうではない人は就職が困難になるといった所得格差が生まれています。
さらに本業のほかにも、インターネットを利用した副業・起業をする人も増加傾向にあり、デジタルデバイドによる所得格差はさらに大きくなることが予想されます。
(3)DX化が進まず生産性が落ちる
デジタルデバイドは、DX化の遅延による生産性の低下も引き起こします。近年はテレワークの導入やインターネットを利用した集客など、各企業でDXの推進が必要不可欠となっています。
しかし、デジタルデバイドによる従業員間の情報格差が、企業のDX推進の足かせとなり生産性の低下を招いています。
企業の生産性が上がらないということは、企業競争が激しい現代において競争に負けてしまう・利益を最大化させられないなどのリスクが考えられます。
(4)企業セキュリティの低下リスクがある
デジタルデバイドは、企業におけるセキュリティの低下を引き起こす可能性があります。
企業において、PCやスマートフォンなど多くのデジタルツールを利用する機会が増えた一方で、それらのデジタルツールにおいては、万全なセキュリティ対策が必須となります。
しかし、デジタルデバイドが加速するとITシステムの管理が不十分となり、情報漏洩などを筆頭に企業におけるセキュリティ面の低下を引き起こす可能性があります。
(5)デジタルデバイドを利用した詐欺や事件が起こる
デジタルデバイドを利用した、詐欺や事件の発生も心配されます。デジタルデバイドを利用した詐欺や事件は、その多くが情報格差のある高齢者を標的としています。
「使用方法がわからない」という理由で、高齢者が一人でデジタルツールを扱う小売店に来店する場合には、デジタルデバイドを利用した詐欺や事件には注意しましょう。
(6)技術や人材が流出してしまう
デジタルデバイドは、国や企業における技術や人材の流出を招きます。デジタルデバイドにより生まれた収入格差によって、国や企業の体制に不満を持った高いリテラシーを持った人材の流出が発生します。
これにより、国や企業ではその多くの割合をリテラシーの低い人材が占める形になってしまいます。
▷デジタル社会に必要な人材と組織とは?現状と実現に向けた課題を解説
デジタルデバイドが起きる7つの原因
デジタルデバイドが起きる原因は、一つとは限りません。以下のような7つの理由で、デジタルデバイドが発生すると考えられています。
- ブロードバンドの整備コストが高い
- 障害時の対応速度・コストが地域によって違う
- IT人材が圧倒的に不足している
- 収入格差によりインターネットが利用できない
- 障がいがあり十分にインターネットを活用できない
- 少子高齢化で若者が地方で働かない
- パソコンが使えない若い世代が増えている
(1)ブロードバンドの整備コストが高い
国や企業がインターネットを利用するには、ブロードバンドの整備が必要不可欠です。しかし、国や企業規模で考えた場合の整備コストは決して安いとはいえないため、ブロードバンドの整備には地域や部署などの費用対効果を考慮する必要があります。
このような過程で、ブロードバンドの整備がされていない地域や部署との間にデジタルデバイドが発生します。
(2)障害時の対応速度・コストが地域によって違う
離島や山間部など、通信障害のトラブル時における対応が遅れてしまう地域では、デジタルデバイドが発生しやすくなります。
このような地域のトラブルに対応するには、人材派遣などが必須になります。このように都市部のトラブル対応と違い、対応速度や金銭的コストがかかることからデジタルデバイドの発生が考えられます。
また、都心部とくらべて地方ではそもそものデジタル人材が少ないこともデジタルデバイトに寄与しているのです。
(3)IT人材が圧倒的に不足している
IT人材不足も、デジタルデバイドにおける原因の一つです。
昨今、日本では圧倒的なエンジニア不足が叫ばれていますが、特に地方ではエンジニアなどのIT人材が不足しており、システム開発やシステムトラブルの対応が困難になっています。
このように、地方ではIT人材の不足によってインフラ整備の進行が鈍化しており、このため都市部との情報格差が拡大しています。
(4)収入格差によりインターネットが利用できない
収入格差によってインターネットが利用できないことも、デジタルデバイドにおける原因のひとつです。
近年、インターネットを利用する手段は、PCだけでなくスマートフォンやタブレットなど複数の利用手段から選択できるようになりました。
高所得者はこのような最新デバイスを簡単に購入できますが、一方で十分な所得がない人の中には、インターネットすら利用できない人もいます。このような収入格差によって、デジタルデバイドが生まれてしまいます。
▷デジタル化が生活にもたらす影響や変化とは?身近な例や現状と今後について
(5)障がいがあり十分にインターネットを活用できない
視覚や聴覚など身体的な障がい、または生まれながらの知的障害などによっても、デジタルデバイドが発生します。
障がいを持つ人は、十分にインターネットを活用できないことが想定されます。このようにインターネットから取得できる情報量に差が出ることによっても、デジタルデバイドは発生します。
(6)少子高齢化で若者が地方で働かない
地方の少子高齢化も、デジタルデバイドにおける原因の一つになり得ます。日本では、働き手となる若者の都市部移住により、地方における少子高齢化が進んでおり、地方の過疎化が問題視されています。
また、日常的にインターネットを利用している若者が減少するため、地方に残される形になった高齢者を中心にデジタルデバイドが発生します。
このように地方の少子高齢化や過疎化も、デジタルデバイドの原因となっています。
(7)パソコンが使えない若い世代が増えている
スマートフォンの操作に慣れている反面、パソコンを使えない若い世代が増えていることも、デジタルデバイドの原因になっています。
企業としては、業務にあたりPCスキルはまだまだ必要不可欠なため、このような若い世代のパソコン離れに対する情報格差を埋めることに苦戦する企業も少なくありません。
▷Z世代とは?何歳から?意味・特徴・由来やX/Y世代との違いを簡単に解説
デジタルデバイド対策で企業ができる取り組み・解決策
デジタルデバイドを減少させるためには、企業は何をすればいいのでしょうか。ここでは、デジタルデバイドを減らすために、企業ができる3つの取り組みや解決策について解説します。
(1)IT教育の機会を設ける
デジタルデバイドを解決するには、企業内でIT教育をする機会を今より多く設けることが大切です。具体的には、次のような取り組みが挙げられます。
- ITに関する研修機会を増やす
- ITスキル向上のために資格取得を推奨する
このように企業におけるデジタルデバイドの解決には、従業員が前向きにITに触れる機会を増やすことが求められます。
(2)デジタルに強い人材を雇用する
すでにデジタルデバイドが進行している企業であれば、デジタルに強い人材を雇用することがデジタルデバイド解決の鍵となります。
また、新規雇用でデジタルに強い人材を確保するとともに、将来のIT人材を育成する目的でプログラミングスクールや地方でのIT教育なども積極的に実施しましょう。
地方自治体と連携を深め、優秀なIT人材の育成環境を整備することも、デジタルデバイド解決においては重要な要素になります。
(3)ITリテラシーの低い社員も使いやすいツールを導入する
DX推進に向けて新規のデジタルツールを導入する際には、ITリテラシーの低い社員に目線を合わせることを意識しましょう。
ITリテラシーの低い社員に照準を合わせることで、多くの従業員が使いやすいツールを選択できるため、ひいては企業におけるデジタルデバイド減少の貢献につながります。
また、初めはITリテラシーが低い場合でもツールやサービスを利用していく中で徐々に仕組みを理解できて、次のステップにつがるケースも十分にあり得ます。
デジタルデバイド対策で自治体ができる取り組み・解決策
ここではデジタルデバイド解消のために、自治体ができる取り組みや解決策を3つ解説します。
(1)スマホの使い方教室を開く
インターネットアクセス手段の主となるスマートフォンの使い方教室を開くことは、地域のデジタルデバイド解消に有効です。
スマホの使い方教室を開催する際には、普段からスマートフォンを上手に使いこなしている地域の高齢者や携帯ショップ、IT企業の社員などにも支援者として協力を仰ぎましょう。
内容については、電源のON/OFFの仕方など、スマートフォンに触れたことのない方を基準に構成することが大切です。
(2)デジタルデバイス購入補助金制度を作る
地域のデジタルデバイス普及のため、補助金制度を設けるのもデジタルデバイド解消に有効です。
地域の高齢者や収入格差のある人にとって、スマートフォンなど高額なデジタルデバイスは、情報格差における原因の一つとなります。
これに対し補助金制度を設けることで、このような層の人たちにも自治体としてデジタルデバイス購入の訴求が可能になります。
(3)コワーキングスペース作成による若者の誘致
地方の過疎化によるデバイスデバイドに対し、コワーキングスペース作成によって若者の誘致も有効です。
コワーキングスペースを作成し地方の若者を誘致することにより、若者がインターネットに触れる機会を作り、そこで習得したITスキルを地方のデジタルデバイド解消に還元するという流れを構築できます。
デジタルデバイドの現状を把握して対策の実施へ
今回は、デジタルデバイドの意味や具体例、懸念される社会的問題などを解説しました。
デジタルデバイドとは、インターネット利用における情報格差のことです。日本におけるデジタルデバイドの現状や、デジタルデバイドを引き起こす問題を把握することで、地域や企業におけるデジタルデバイドの拡大を抑制できます。
デジタルデバイド解消に向けた取り組みは、企業や地域などの各場面で多岐にわたります。まずはデジタルデバイドの現状把握に努め、その上でデジタルデバイドの対策を実施しましょう。
デジタル化の記事をもっと読む
-
ご相談・ご質問は下記ボタンのフォームからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
 ログイン
ログイン