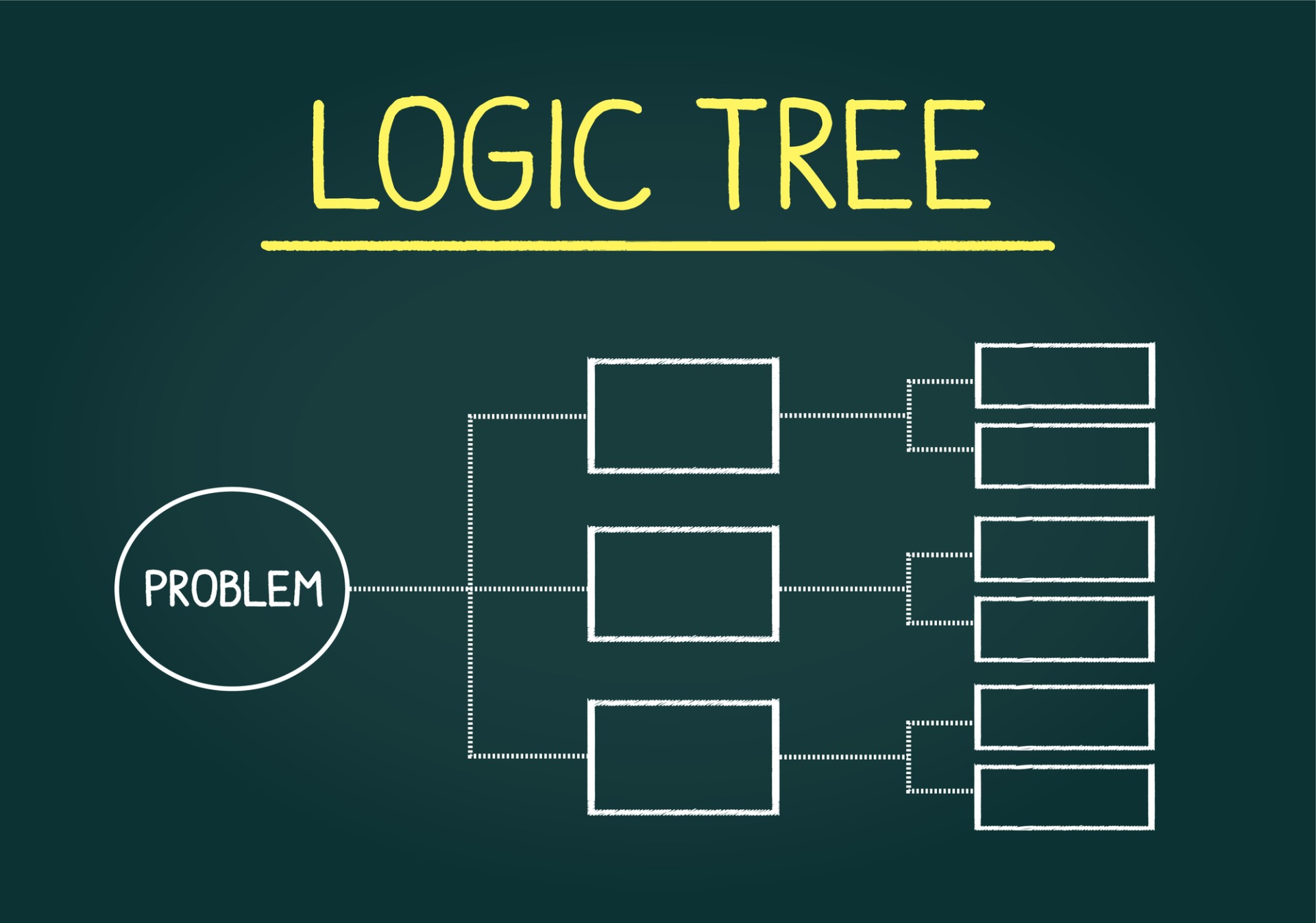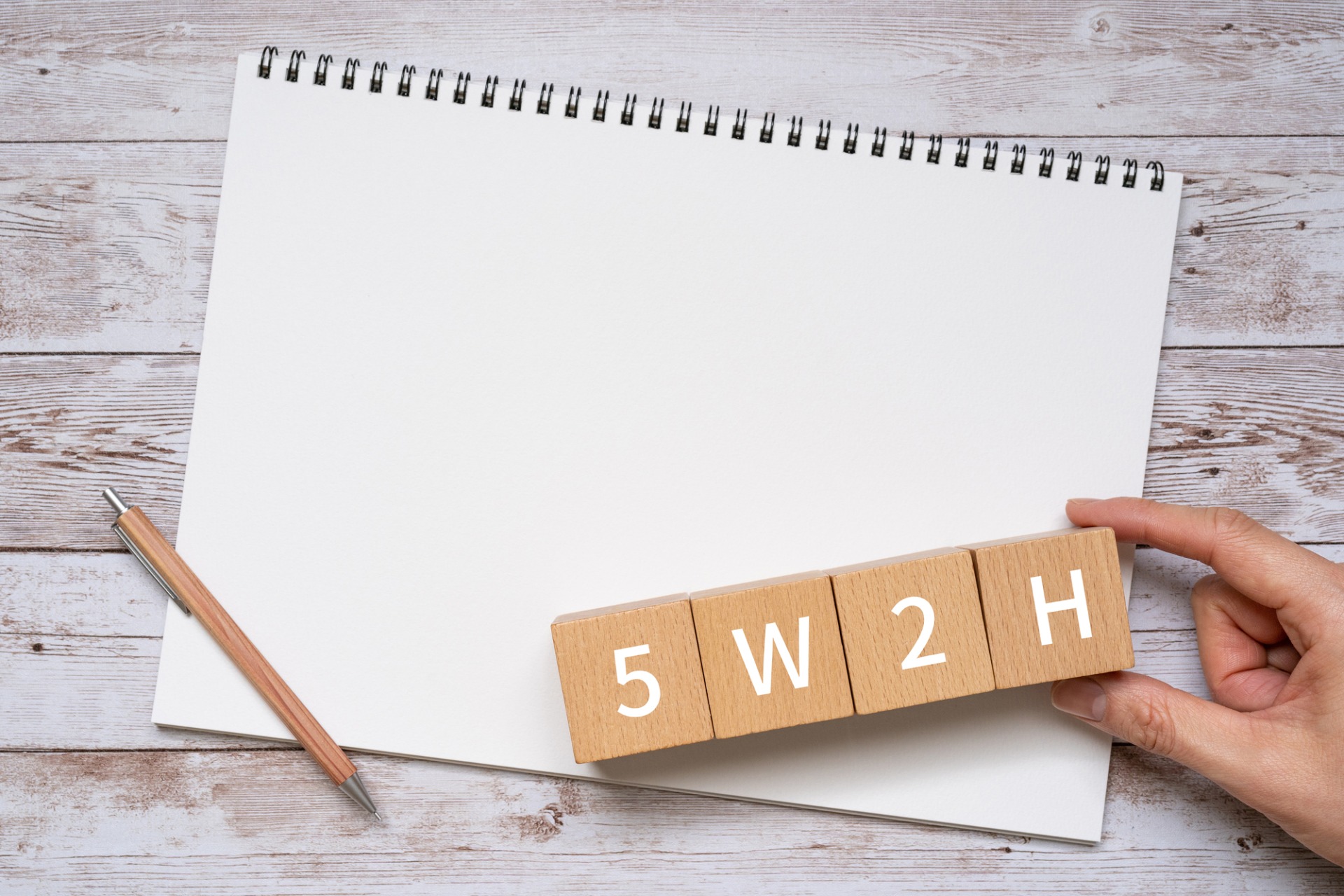PDCAは古い?注目されるOODAループとの違いやDCAP・PDRを紹介!

変化の激しい現代において、もはや古いと言われているPDCA。ニューノーマルな時代に適応するには、新たに注目されるOODAループの活用が必要です。本記事では、OODAループやPDCAが古いと言われている理由、その他の手法について紹介していきます。

監修者 福本大一 株式会社kubellパートナー アシスタント事業本部|ユニット長 大学卒業後、toC領域のWEBメディア事業で起業。事業グロースに向けたSEO戦略から営業・運用広告に従事し、約2年間の経営を経て事業譲渡。2021年3月からChatwork株式会社(現:株式会社kubell)に入社し、カスタマーマーケティングやアライアンスを経験した後、メディア事業・運用広告事業の責任者としてミッションを遂行する。現在は、DXソリューション推進部のマネージャーとして新規事業領域のセールス・マーケティング・アライアンス・メディア事業を統括。
目次
そもそもPDCAとは?
PDCAとは業務の生産性向上を目指して業務の改善を進めていくためのフレームワーク・手法のことです。特に新入社員の時に耳にすることが多い言葉でもあります。
なお、PDCAは下記4つの英語の頭文字をとっています。
- 「Plan」:計画
- 「Do」:実行・行動
- 「Check」:評価・確認
- 「Action」:改善
PDCAの各プロセスについて紹介していきます。
Plan:計画
PlanではPDCAのスタート部分であり、目標を定めた上でその目標を達成するための計画を立てていきます。目標を達成するためにはどのような行動が必要なのか、何を考えるべきなのかなどを、より具体的に設定するのが重要です。
Planが抽象的になってしまうと、行動していく中で不明確な部分が出てきてしまい、うまくサイクルが回せなくなります。具体性を持たせるためにも数字や期日を設けるなどより具体的になるような工夫が大切です。
Do:実行
DoではPlanで立てた目標に対して具体的に行動していきます。ただ行動するだけではPDCAの意味合いがなくなってしまうため、時間を計測したり、どのような課題があったかなどを記録しておくと良いでしょう。
細かい記録を残しておくことによって、振り返りや分析、改善策が見つかりやすくなります。
Check:評価
CheckではDoで実施したアクションが達成できたかを確認して評価するフェーズです。アクションが達成できた場合にはどの点が良かったのか成功要因を分析し、失敗した場合には失敗した要因を分析して言語化します。
物事の失敗・成功となる結果だけで判断するのではなく、行動そのものを評価することによって、次のActionで具体的な改善策を見つけることができます。
Action:改善
ActionではPlan・Do・Checkで分かった改善すべき点を考えこのまま計画を進めるべきなのか・新しい計画を立てるべきなのかなど、今後の改善方法を決めていきます
このActionで決めた今後の方針をふまえ、次の行動に移して持続的にサイクルを回していくことによってより業務効率をアップさせることができるのです。
▷PDCAとは?サイクルを回す重要性やポイント・失敗する原因を解説
▷PDCA実践シートの書き方と記入例を解説【テンプレート紹介あり】
PDCAが古い・時代遅れと言われている理由
PDCAは1950年代にアメリカの統計学者によって提唱された考え方です。70年以上前に提唱された考え方ですが、現在でもPDCAを活用している人や組織は多いでしょう。しかし、最近ではPDCAの考え方はもう古いとも言われています。
次にPDCAがもう古いと言われている理由について解説します。
改善までに時間がかかり過ぎる
PDCAが古いと言われている理由は、P(プラン)に時間をかけすぎてしまい、早いサイクルで回すことができないためです。近年はIT技術の進化によって世の中が猛スピードで変化・発展しています。そのため、企業競争に勝ち残るにはスピードが非常に重要です。
しかし、PDCAを活用する人の中には、「P」の計画(Plan)に多くの時間を割く人がいます。変化が激しい現代で消費者の本当のニーズを捉えるには、実行して生の声を聞きながら改善していくことが必要になります。PDCAで計画に時間をかけている場合、改善のスピードも遅くなってしまいます。
このように、スピードが重要視される現代で、PDCAは時間がかかることから古いフレームワークと言われるようになりました。
サイクルを回すこと自体が目的になってしまう
PDCAサイクルを回すことの本来の目的は、設定した目標を達成することです。しかし、PDCAサイクルを回しているうちに、PDCAサイクルを回すこと自体が目的化してしまうことがあります。
本来評価するべきことは目標達成に近づいているかが重要にもかかわらず、PDCAサイクルを回せているかどうかで評価してしまっているといったケースもあります。
PDCAサイクルは目標達成をするための手段にすぎません。「いつまでに何を達成させたいのか」といったことを明確にしたのちに取り組むことが重要です。
▷PDCAを重視しているのは日本企業だけ?生じる弊害や最新手法について
PDCAに代わる新たな手法「OODAループ」
「OODA(ウーダ)」とは以下の意味を持っています。
- 「Observe」:観察
- 「Orient」:状況判断
- 「Decide」:意思決定
- 「Action」:行動・改善
ポイントは綿密に計画を立てるのではなく、観察して瞬時に状況判断して実行するかしないかを意思決定することです。OODAループを活用することで、スピード感を持って取り組むことが可能になります。
Observe:観察
Observeでは既存の固定概念に執着せずに競合や市場を入念に観察してデータを収集するフェーズで、観察する上ではどのようなニーズがあるのかを見極めるのが重要です。
広い視野を持ってより柔軟に対応することによって、以前では発見できなかったニーズを発見することができます。
Orient:状況判断
Orientでは観察したことから得た情報をもとにして、現在の状況を判断して何をしていくべきなのか方向性を定めます。
このステップで時間をかけすぎてしまうと、サイクルを回すのが遅くなってしまうので、できるだけ早くスピードを意識していくのが非常に重要です。
Decide:意思決定
DecideではOrientで決定した方向性や方針から、具体的に何をしていくべきなのかを決定します。また、行動に移す前の段階なので最終的な意思決定も含まれています。
なお、様々な意見が出揃っている段階でもあるので全ての情報をわかりやすく集約して最も効果がある方法はどれか選択していきます。
Action:行動・改善
ActionではDecideで決定した計画をもとに具体的な行動を進めていきます。進める際には、必ずしも施策に固執する必要はなく、ニーズの変化・成功する見込みが薄いと判断した場合には改めてOODAループを回していくのも重要です。
▷MECE(ミーシー)とは?論理的思考法のフレームワークを具体例で解説
OODAループとPDCAサイクルの違い
OODAループとPDCAサイクルには以下のような違いがあります。
- OODAループ:状況を見てとりあえず行動に移す
- PDCAサイクル:綿密に計画を立ててから行動に移す
OODAループとPDCAサイクルでは、行動に移すまでのスピードが異なり、OODAループの方がスピードが速く、かつ柔軟性を持って取り組むことができます。
そのため、行動前の段階で時間をかけすぎてしまうとその後の行動も全て遅くなってしまうため、様々なことが急速に変化していく現代においてはOODAループを採用している企業が多いのです。
▷PDCAの問題点とは?注意すべきデメリットや致命的欠陥について
OODAループを実践するメリット
OODAループを実践することには以下の3つのメリットがあります。
- 変化にも柔軟に対応できる
- スピード感を持って実行できる
- 顧客ニーズの変化に対応できる
それぞれのメリットについて解説します。
変化にも柔軟に対応できる
OODAループは、実際の現場や状況を観察して意思決定するため、世の中の変化に柔軟に対応することが可能です。大きな変化が起きた場合でも、現場で働く社員が状況を観察し、短時間で意思決定して行動・改善できるようになります。
スピード感を持って実行できる
PDCAサイクルはしっかり計画を立てた後に行動に移します。一方で、OODAループは現状を観察した後に、とりあえず行動に移すという考え方であるため、スピード感を持って実行に移すことができます。
IT技術が発展している現代では、入念に計画を立てている段階で、すでに変化が起きているといったことはよくあることです。
現代の企業競争で勝ち進むためにはスピードが非常に重要になりますが、OODAループを活用することでスピード感を持って実行できるようになります。
顧客ニーズの変化に対応できる
OODAループは、「今」を観察してすぐに実行します。そのため、顧客ニーズの変化に対応した素早いアクションが可能になります。
世の中の変化に伴って顧客ニーズは刻々と変化します。そして、企業は顧客のニーズに対応し続けなければ競争に勝ち残ることができません。
OODAループを活用することで、顧客ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供し続け、企業競争に勝ち残る可能性を高めることができます。
▷業務効率化・業務改善に役立つフレームワーク10選!活用法まで解説
OODAループを実践するデメリット
OODAループには以下の3つのデメリットがあります。
- 孤立してしまう可能性がある
- 組織の統制が取りにくくなる
- 情報収集に費やす時間が減ってしまう
それぞれについて解説します。
孤立してしまう可能性がある
OODAループを活用すると、裁量権が個人に委ねられるといったこともあり、個人が業務や責任を抱え込み、孤立してしまう可能性があるのです。
OODAループを取り入れる際は、チーム内でのサポートが重要になります。個人が業務や責任を抱え込む可能性がある場合はチーム内で業務を割り振ったり、引き取ったりするなどのサポートをすることが大切です。
組織の統制が取りにくくなる
OODAループは個人に裁量権が委ねられることがあるため、チームとして動くのではなく、個人プレーになってしまう傾向があります。そのため、組織内でも目標や行動が個人によって異なり、組織の統制が取りにくくなることがあります。
組織の統制を取るためにも、それぞれの目標や目標を達成するための行動などを共有する機会を設けることが大切です。組織である以上同じ目標を目指す必要があります。
そのため、目標や行動を共有し、間違っている場合は指摘し改善を図りながら、組織の統制を取ることが大切です。
情報収集に費やす時間が減ってしまう
OODAループは観察してすぐに状況判断・意思決定し、実行に移します。スピード感を持って実行に移すことができるのは大きなメリットですが、情報収集する時間が減るといったデメリットもあります。
何に取り組むにしても情報収集は必要です。情報収集しないままOODAループを回し続けると、意思決定にミスが生じて間違った方向に進んだり、意思決定ができなくなったりします。
一人で十分な情報を収集することが難しい場合は、組織内で情報を共有し合う機会を設けることで、効率的に情報収集することが可能になります。
▷業務改善のアイデア出しにおけるポイントは?効果的な手法を紹介
PDCAとOODAを使い分ける方法とは?
PDCAとOODAは場面によって使い分けることが重要です。具体的には、変化の少ない市場で競争する場合はPDCAを活用し、一方で変化の激しい市場で競争する場合はOODAを活用します。
例えば、IT技術では代替されにくい業界や生活必需品を扱う業界などは短期間で大きな変化を遂げる可能性が極めて低い市場です。そのような業界に属し、既存商品やサービスの提供数を拡大させたい場合は、よく計画を練り、実行、評価、改善を繰り返すPDCAが有効です。
一方で、ITやインターネットを扱う業界は、短期間で大きな変化を遂げます。そのため、現状を観察し、短時間で意思決定・実行に移すOODAが有効になります。
重要なことは手段にこだわるのではなく、場面に応じてPDCAとOODAを使い分けることです。「P(=Plan:計画)」または「O(=Observe:観察)」を実行する前に、どちらの手段を活用するのが適切なのかよく考える必要があります。
▷個人で取り組める業務効率化アイデア14選!便利なツールも紹介!
PDCAの代わりに注目されるその他の手法
PDCAの代替手段として注目されている手法は、OODA以外に以下の2つがあります。
- DCAP
- PDR
それぞれの手法について解説します。
DCAP
DCAPには以下の意味があります。
- 「Do」:実行・行動
- 「Check」:評価・確認
- 「Action」:改善
- 「Plan」:計画
4つの要素はPDCAと同様ですが、DCAPは「Do」の実行から始めます。PDCAの場合は最初に計画を立てるため、一次情報が少ない状態で計画を立てて実行するという流れでした。また、実際はサイクルが成立せず、単発でPDCAを回すといったケースもよく見受けられます。
一方で、DCAPは最初に実行することで、実行したことで得られた一次情報をもとに計画を立てられるようになります。DCAPを活用することで、計画の精度を高めたり、後戻りを防いだりすることができます。
PDR
PDRは新規事業を開発するときや、斬新かつ有効なビジネスアイデアを考えるときなどに活用します。PDRには以下の意味があります。
- 「Prep」:準備
- 「Do」:実行・行動
- 「Review」:評価
PDCAのPは「Plan(計画)」でしたが、PDRの場合は「Prep(準備)」になります。準備段階では「どんな事業をするのか」「どんな理由でその事業をするのか」などを考えます。考えるべきことは数値目標ではなく、事業内容やその事業をする理由などです。
準備をした後に実際に行動をして「Review(評価)」します。評価の段階では「できた」「できていない」だけでなく、第三者からの意見やアドバイスをもらうことが重要になります。
上記のPDRサイクルは、1回のスパンが短いため素早く改善できるようになったり、第三者の意見を取り入れて正しい方向に改善できるようになるといったメリットがあります。
▷マンダラートとは?目標達成や業務改善に役立てるメリットや作り方
PDCAとOODAを適切に使い分けて活用すること
本記事ではPDCAサイクルに代わるOODAループやDCAP、PDRについて解説しました。重要なのは、場面に応じてそれぞれのフレームワークを使い分けることです。
あくまでも手段であるため、手法に固執したり、フレームワークの実行自体を目的化しないように注意する必要があります。本記事を参考にして、自社のビジネスを成功に導く手法を使い分けながら、活用しましょう。
業務効率化・業務改善の記事をもっと読む
-
ご相談・ご質問は下記ボタンのフォームからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
 ログイン
ログイン