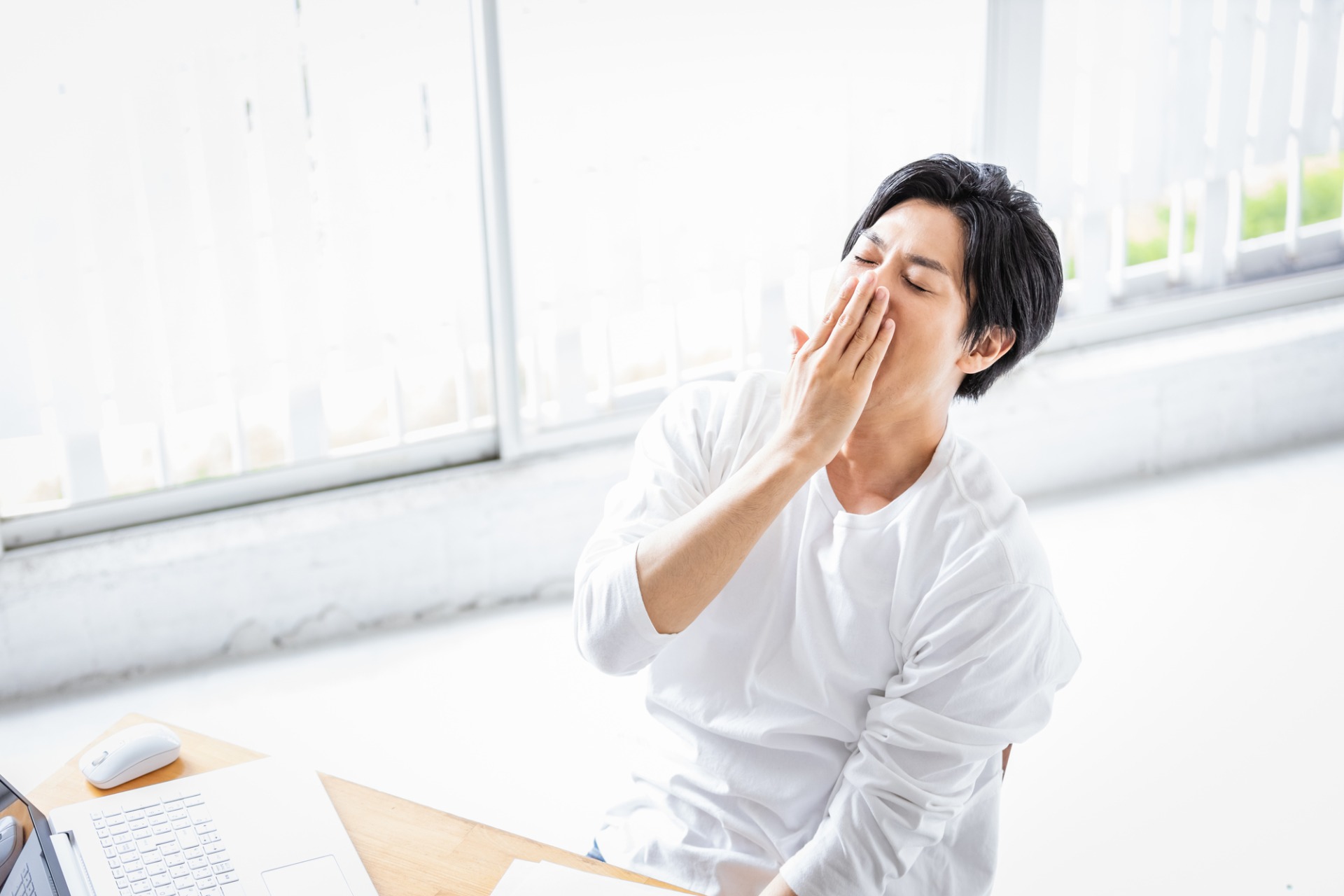テレワークうつの危険性とは?増加している原因や症状の特徴・予防法を解説

近年、テレワーク環境におけるストレスから精神的な不調を訴える人が増え、「テレワークうつ」といった言葉も耳にするようになりました。本記事では、テレワークうつの危険性や原因を解説するとともに、テレワーク時代における心のケア・対策方法について詳しくご説明します。
目次
テレワークに潜む「テレワークうつ」の危険性とは
テレワークには、従業員のワークライフバランスの向上や、ワークエンゲージメントの向上による生産性アップなど、多くのメリットがあります。しかしその一方で、これまでのオフィス勤務とは大きく異なる環境に対して、深刻なストレスを感じている人が存在するのも事実です。
「テレワークうつ」とは、テレワークという労働環境により発生するストレスが原因で、気分の落ち込みから抜け出せないことや、感情をコントロールできない、眠れない、食欲がないといった心身の不調が生じる状態を意味しています。
テレワークの場合、一人で仕事をこなすケースが多く、不調のサインに周囲が気づきにくいことから、「サイレントうつ」と呼ばれることもあり、気づかぬうちに症状が深刻化してしまうリスクが高いとされています。
▷テレワークは当たり前になる?今後の変化と未来の働き方について
「テレワークうつ」が増加している原因
国土交通省が行った「テレワーク人口実態調査」では、テレワーク勤務を行う実施者の約8割が「テレワークを継続したい」としている調査結果が出ています。
大半が、テレワークを快適だと感じている状況が伺えるなかで、なぜテレワークうつの増加が懸念されているのでしょうか。ここでは、その原因を詳しく解説します。
1.コミュニケーション機会の減少
テレワークの代表的なデメリットとも言えるのが、コミュニケーションの取りづらさやコミュニケーション機会の減少です。
一人で黙々と作業を行うことが苦でなければ、大きなストレスとはならないかもしれません。
ただし、仕事の合間のちょっとした雑談による息抜きが、モチベーションの維持に役立っていたり、疑問を共有したりする良い機会になっていたというケースは珍しくありません。
しかし、テレワークでは、相手の様子が伺えないことから、些細な悩みを打ち明ける場がなく、一人で抱え込んでしまいがちです。このようなコミュニケーション不足による強い孤独感は、長引くことにより不安やストレスを引き起こし、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼすといわれているのです。
▷テレワークでコミュニケーション不足になる原因とは?解決するための対処法
一人暮らしの場合は特にコミュニケーションが減少する
自宅に家族がいたり、同居人がいる場合には社内でコミュニケーションがなくても会話する機会があります。しかし、一人暮らしの場合は仕事中のコミュニケーションはもちろん、終業後に会話する機会もありません。
1日で誰とも会話をしないという状況もあり、慢性的にコミュニケーションが取れなくなります。結果的に、複数人で暮らしている場合と比べてストレスや不安を溜め込んでしまいテレワークうつを引き起こす可能性があるので十分に注意が必要です。
2.オンオフの切り替えが難しい
テレワークでは普段生活している環境で仕事をしなければならないため、仕事のオンオフの切り替えが難しい傾向があります。
仕事に集中できないのはもちろん、休みの日も仕事のことを意識してしまったり、深夜に仕事をしたりとプライベートの時間が充実しなってしまうケースもあるのです。
結果的に長時間労働や生活リズムの乱れを引き起こしてしまい、テレワークうつを引き起こす要因となってしまいます。
3.運動不足による身体の不調
適度な運動は、不安や憂うつな気分の改善、ストレスの解消にも効果が期待できるといわれています。
その上で、オフィス勤務時には、通勤のほか、取引先への訪問、社内における部署間や会議室の移動など、日常的に体を動かす機会が発生していました。
しかし、テレワークにおいては、これらの身体活動がほぼなくなってしまいます。意識的に体を動かすことがなければ、家から一歩も出ない日が続いてしまうこともあるでしょう。
また、テレワークでは、会議や打ち合わせもオンラインで実施されることが多く、必然的に長時間の座り姿勢を強いられることから、肩こりや腰痛に悩まされているという人も多いようです。
4.仕事環境が整っていないことによるストレス
オフィスでは、多くの場合、デスクやチェアなど自分専用のワークスペースがあり、PCなど、仕事に必要な機器も全て揃っているかと思います。
しかしテレワークの場合、特に、家族と同居しているケースにおいては、仕事専用のスペースを確保することすら難しく、集中しにくい環境にて業務を行うことも珍しくはありません。
生活音が気になったり、家族の動き回る気配が集中の妨げになることもあるでしょう。
このような環境のなか、なかなか業務の効率や生産性を上げられないことに苛立ちを感じ、ストレスを募らせてしまうこともあります。
▷テレワークによるストレスの原因とは?ストレスを解消する方法も紹介!
「テレワークうつ」の主な症状
テレワークうつは、心と身体におけるさまざまな症状として表れます。
これらに当てはまっているからといって、即座に医学的な病名である「適応障害」や「うつ病」といった診断を受けるわけではありませんが、状況によっては専門家による正しいケアを必要とする場合もあるでしょう。
また、周囲の人に、以下のような症状が見受けられる際にも、コミュニケーションの機会を設けたり、場合によっては、本人の希望を聞いた上で産業医との面談をセッティングするといった配慮が求められることになります。
1.身体的に現れる症状
テレワークうつによる、身体的な症状には、以下のような例が挙げられます。
- 食欲の変化(食欲不振・食欲過多)
- 睡眠障害(不眠・過剰睡眠)
- 内臓の不調(胃もたれ・下痢・便秘)
- 痛み(頭痛・肩こり)
- 慢性的な疲労感や倦怠感
- その他(耳鳴り・動悸・めまい・眼精疲労・口が渇く・冷や汗・震え)
2.心の面に現れる症状
次に心の面に現れる、テレワークうつの症状やサインの例は、以下の通りです。
- 長引く憂うつ感感
- 極端な悲観的な思考
- 理由のない不安感や焦燥感
- イライラ
- 無気力・無関心
3.他人から見た症状
テレワークうつの症状の中には、当人よりも先に、周囲がその変化に気づけるケースもあります。
以下のような症状が見受けられた場合には、コミュニケーションの機会を設けるなど、適切な対応をするようにしましょう。
- 遅刻・早退・欠勤などの増加
- 飲酒量が極端に増える
- 極端な悲観的思考
- 感情の起伏の激しさ
- 無表情
▷テレワークで増加する体調不良とは?原因や企業・個人が取るべき対策方法
「テレワークうつ」の効果的な対策と予防法
心身に深刻な影響を及ぼしかねないテレワークうつは、誰でも発症する可能性があります。
ここでは効果の期待できる予防方法を、4つご紹介します。「最近疲労感が抜けない」といった自覚症状が現れ始めたら、無理のない範囲で予防策を実践してみましょう。
1.オン・オフの切り替えを大切にする
仕事とプライベートを分けて、オンとオフの切り替えを意識的に行うようにしてみましょう。
仕事専用の部屋やスペースを設けるのが望ましいと言えますが、スペースの確保に関しては、住環境の事情から難しいこともあります。
その場合は、在宅勤務であってもビジネスシーンにふさわしい服装に着替えるといった物理的な変化をきっかけにすると良いでしょう。
また、家族には在宅であっても「仕事中」である点を理解してもらい、「ワークングスペースには立ち入らない」「仕事中は話しかけない」といった勤務中のルールについて、話し合っておくことも重要です。
▷テレワークはずるい?在宅勤務でよくある社員の不満の理由と対策について
2.日常的なコミュニケーションを徹底する
テレワークにおける、孤独感や孤立感は、コミュニケーション機会のルール化により、リスクを軽減することができます。
議題や懸念事項がなくても、週1回のビデオ会議をルーティンに組み込み、ラフなコミュニケーションの場を設けるようにすると効果的です。
また、完全なテレワーク化であっても、定期的な「オフライン」ミーティングの実施が、組織の風通しの向上に役立つこともあります。
カジュアルなコミュニケーションが活発になれば、従業員同士が、お互いの変化に気づきやすい環境づくりにもつながるでしょう。
3.始業・終業時間を意識する
フレックスタイム制によるテレワークの場合、オフィス勤務時と違って、始業や終業の時刻に対する意識が薄れてしまいがちです。ダラダラと仕事を続けてしまった結果、深夜帯の労働が常態化してしまい、生活リズムを崩してしまうケースは少なくありません。
長時間労働を習慣化させないためにも、始業時間・就業時間を意識して自らで働く時間をコントロールするようにしましょう。
労働時間をコントロールするためには、始業時にTodoリストを作成しておき、どのような業務を何時までに終えるのか明確に定めておくことが非常に重要となります。
▷テレワーク導入の際に就業規則の変更は必要か?手順や注意点を徹底解説
4.しっかりと休む
睡眠などの休息は、「量」だけでなく、その「質」も心身の疲れを癒す重要な要素です。
規則正しい睡眠時間や適度な運動などの生活習慣を身につけるほか、就寝前は、スマホやパソコンを操作しないなどの睡眠前の行動も、睡眠の質を左右する要素と言われています。
睡眠時間さえ確保すればOKとするのではなく、安定した睡眠を得るための生活サイクルを習慣化するようにしましょう。
企業側がすべきテレワークうつ予防のための取り組み
テレワークうつを予防する上では社員個人だけに任せるのではなく、企業側が率先して予防するための取り組みをすることが重要です。
社員のコミュニケーションが活発になるような環境を整える
テレワークではオフィス勤務と比べてコミュニケーションをとるシーンが減少してしまい、社員間でもコミュニケーション頻度はまばらになってしまいます。
そのため、オンライン上で社員同士が会話できるような機会を設けたり、オンラインでのランチ会を開催したりとコミュニケーションが取れるような環境を整えましょう。
少ない時間でも定期的に社員間のコミュニケーションを促すことによって、自発的にコミュニケーションが取れるようになるでしょう。
ストレスチェックのアンケートを定期的に実施する
テレワークでは社員のストレス状態を把握しにくいため、定期的にストレスチェックアンケートを実施するのも大切です。
アンケートの回答結果を集計することによって、各社員のストレス状況を確認できて素早いフォローをすることができます。アンケートの頻度は定まっていませんが、月に1度のペースが好ましいでしょう。
▷テレワークで集中できない原因とは?集中するための対策や集中力アップの秘訣
▷テレワークでコミュニケーション不足になる原因とは?解決するための対処法
「テレワークうつ」の可能性がある場合
先に紹介した症状があらわれ、テレワークうつの可能性が疑われる場合には、生活リズムの見直しを行うだけでなく、サインに気づいた早い段階で同僚や先輩、上司などに相談するようにしてください。
心身の不調が適応障害やうつ病に発展してしまうと、多くの場合、治療なしでの回復を見込むことは困難であり、長期間にわたる治療を要する結果となってしまいます。
周囲が声かけをかけやすい環境を整えておくこと、また組織としても相談窓口の開設や、産業医との連携による対応をしていくことが大切といえるでしょう。
▷テレワークで社員のモチベーションは低下する?原因と対策方法10選
「テレワークうつ」は早期発見が重要!組織体制の見直しを
本記事では、テレワークうつの原因や予防策について詳しく解説しました。
テレワークうつは、その環境から初期症状に周囲が気づけないことや、症状によっては「サボり」と勘違いされ放置されてしまうことがあります。
しかしながら、テレワークうつによる症状は、放っておくと深刻な精神疾患の引き金となってしまう可能性もあるのです。
従業員一人一人の自己管理も大切ですが、それと同時に人によってテレワークの環境に大きなストレスを感じるケースがあることを組織が把握することが重要です。
組織においても、テレワーク特有の従業員の悩みに対応できる仕組みを構築し、テレワークうつのサインを早期発見できる環境を整えるようにしましょう。
テレワークの記事をもっと読む
-
ご相談・ご質問は下記ボタンのフォームからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
 ログイン
ログイン