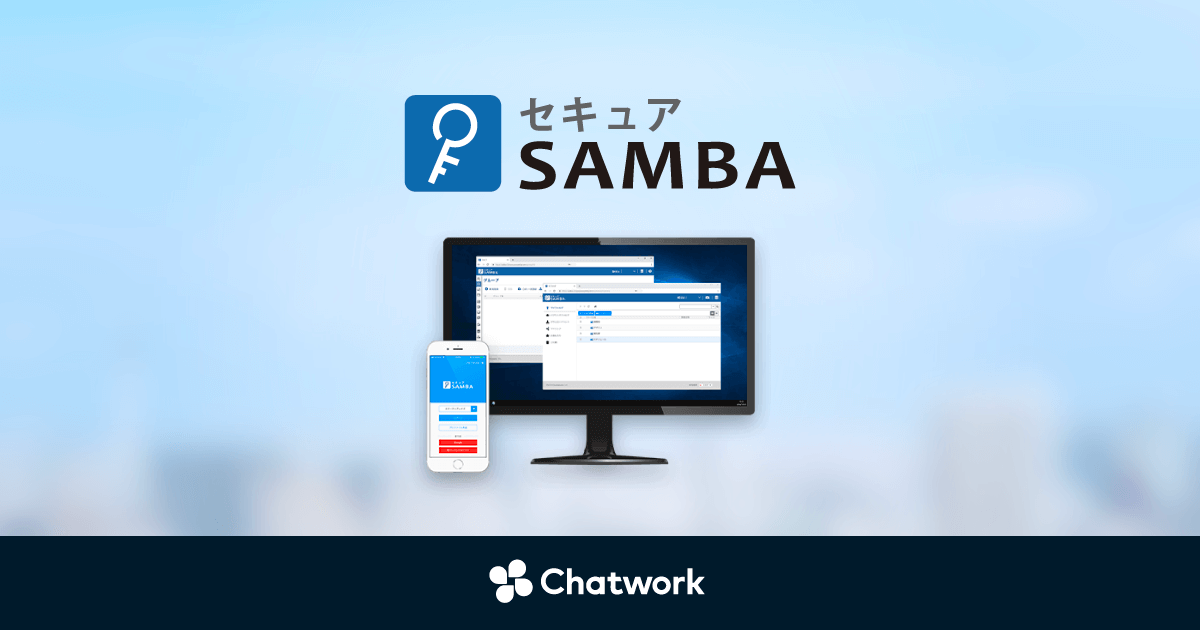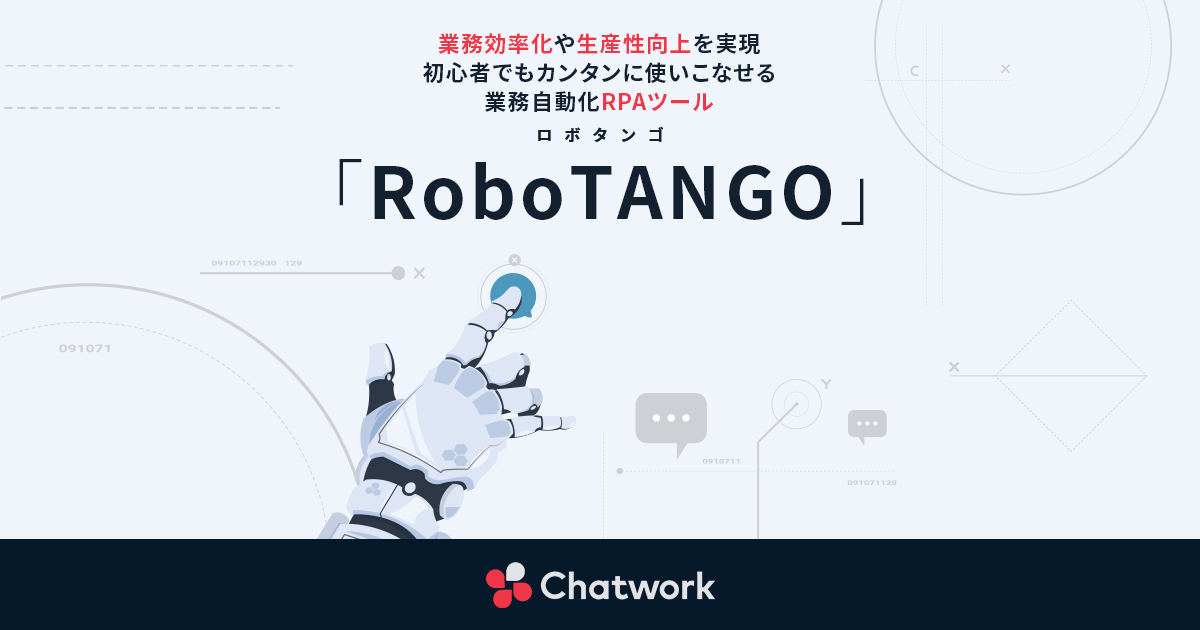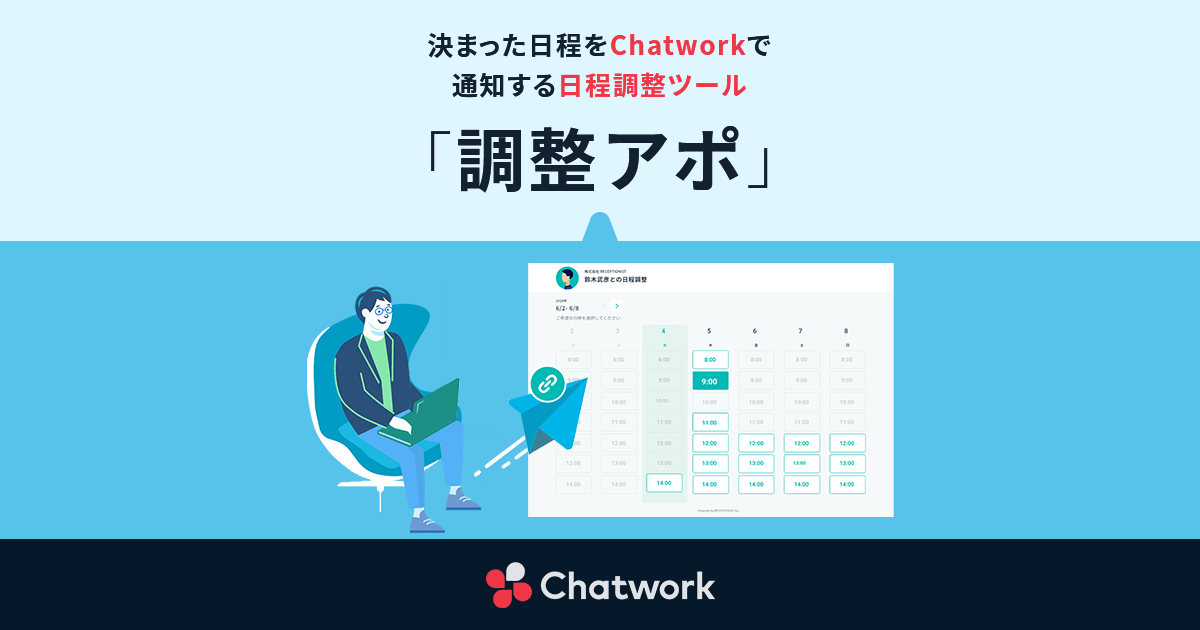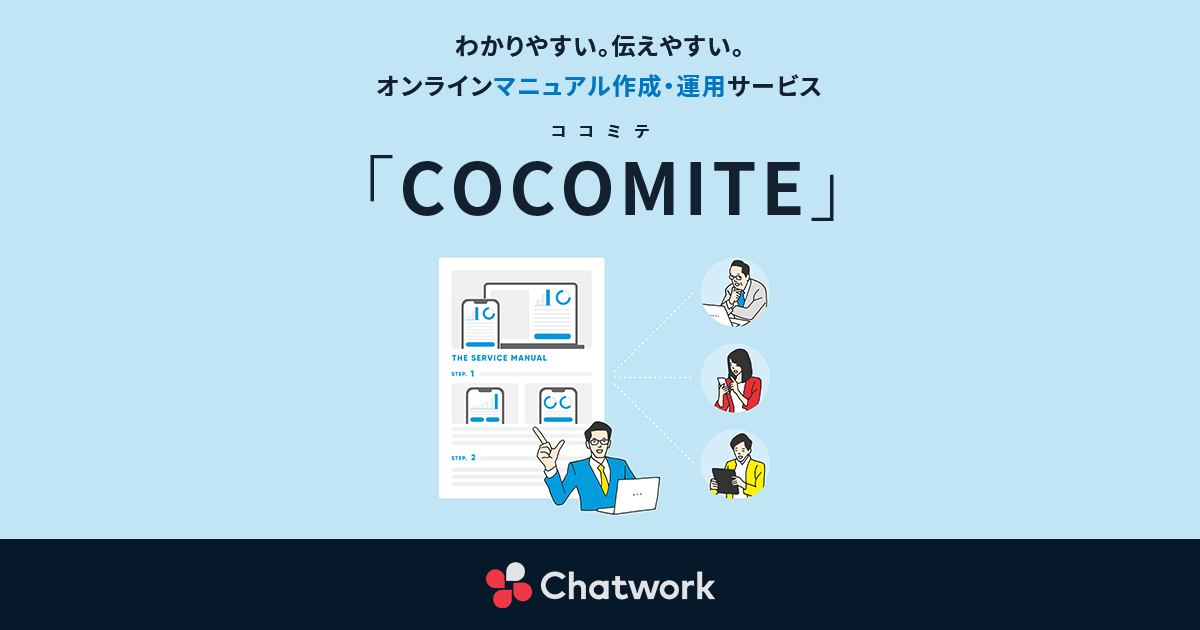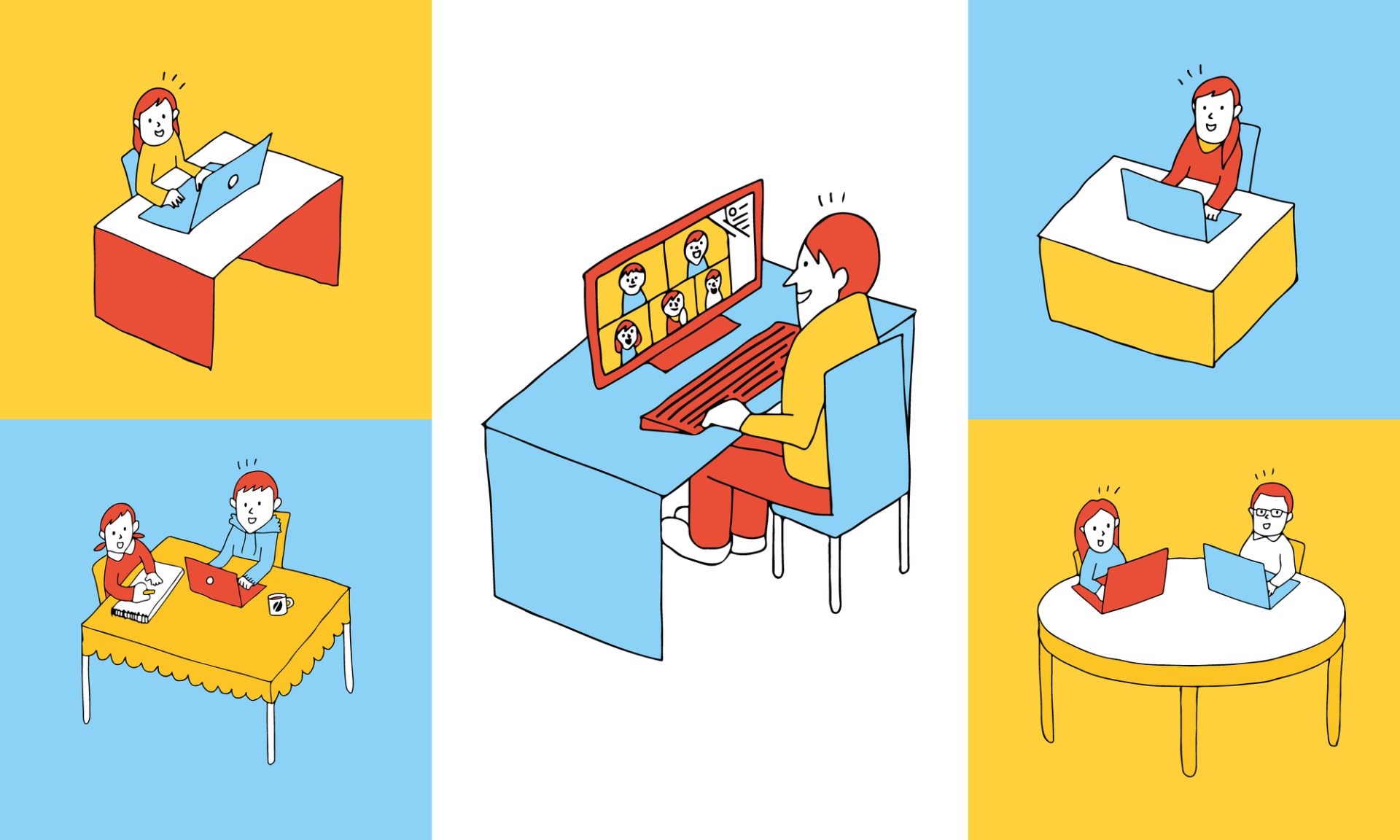テレワークにおける健康問題|リスクや課題・健康管理の方法を解説

近年で日常化してるテレワークでは、オフィスワークと働き方が異なることから様々な健康問題が考えれられます。しかし、健康への意識を保つのは難しく、企業としても管理が難しい側面があります。この記事では、テレワークにおける健康問題や健康管理の方法について紹介していきます。
目次
テレワークにおける健康管理の重要性
オフィスワークと同様に、テレワークにおいても働く人の健康管理は重要です。さらに、在宅勤務で顔が見えないテレワークこそ、従業員の健康を守るために十分な注意を払う必要があるともいえるでしょう。
また、労働に関する最低条件を定めた「労働基準関係法令」がテレワークにも適用されることもテレワークにおける健康管理が重要な理由の一つとされています。
労働基準関係法令がすべて適用される
テレワークによって、就業場所がオフィスから自宅に変わっても労働基準関係法令は適用されます。
具体的には「労働基準法」や「労働安全衛生法」などが該当しており、それぞれの概要は以下のとおりとなっています。
労働基準法
労働三法の一つである労働基準法は、主に下記の労働条件における最低基準を定めたものになります。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休日および年次有給休暇
- 災害補償
- 就業規則
もし、テレワークをしている従業員の労働時間が把握できておらず、従業員が休日や休み時間も仕事をしていれば、長時間労働となる可能性が生じます。
場合によっては労働基準法に違反し、企業が過重労働をさせているとみなされる恐れがあります。
▷【重要】勤怠管理で知っておくべき労働基準法の基本ポイントを解説
労働安全衛生法
労働安全衛生法とは、従業員の安全や健康を確保し、快適な職場環境にするために制定された法律です。具体的には以下のようなルールがあります。
- 定期健康診断結果報告書の提出
- ストレスチェックの実施
これらの法律はオフィス勤務者だけでなく、テレワークで働く従業員にも該当するものです。
重要視される「安全配慮義務」とは?
テレワークにおいて重要視すべきと考えられているのは「安全配慮義務」です。
安全配慮義務とは、「従業員が労働する際に健康や安全を確保する」といった企業の義務を定めたもので、労働契約法第5条に記されています。
例えば長時間労働を続けている従業員には、医師による面接指導を行わなければなりません。企業がこうした取り組みを行うことで、働く人の健康が守られ、安全配慮義務を果たすことができるとみなされているのです。
これはオフィスワークに限らず、従業員の顔が見えないテレワークにおいても必要な取り組みでしょう。
▷テレワーク中に労災は適用される?認定条件や注意点を事例も踏まえて解説
▷テレワークに関連する助成金・補助金まとめ!該当基準や申請方法も解説
テレワークでの健康リスクへの影響
テレワークを行うことで、以下のような健康リスクが発生することが懸念されています。
- 運動不足や筋力の低下
- 生活習慣病への影響
- メンタルヘルスへの影響
無理な働き方をしている従業員に対して指導などの対応をしていない場合は、体調不良に繋がる懸念があります。
特に、働く人の顔が見えないテレワークで、従業員の健康を維持することは難しいため、企業はあらかじめテレワークのリスクを知っておくことが大切です。
運動不足や筋力の低下
オフィスに通勤していた頃とは違って、駅まで歩いたりフロア内を移動したりする機会が減り、運動不足のリスクが考えられます。運動量が極端に少なくなってしまうと、肥満や筋力の低下などに繋がることも懸念されます。
また、運動量の低下は筋力不足だけではなく、姿勢が悪くなったり肩こり・腰痛などの原因にもなるでしょう。慢性的な運動不足になると、仕事だけではなく、日常生活にも支障をきたしてしまうケースも考えられます。
▷テレワークによって運動不足になる?健康への影響や解消方法を紹介
▷テレワークで腰痛になる原因は?すぐ実践できる対策法や椅子の選び方を解説
生活習慣病への影響
テレワークで運動する機会が減ると、肥満のリスクが高まることも心配されています。「肥満は万病のもと」といわれますが、肥満は以下のような生活習慣病の発症リスクを高めます。
- 糖尿病
- 高血圧
- 脂質異常症
さらに、持病がある場合はこれらの症状が引き金となり、元々持っている病気が重症化する危険性もはらんでいます。このように、テレワークによる運動不足がもたらす健康へのダメージは大きいと考えるべきでしょう。
▷テレワークで増加する体調不良とは?原因や企業・個人が取るべき対策方法
メンタルヘルスへの影響
テレワークが長期化すると、身体面だけでなく精神面で不安定になる従業員が増えることも危惧されています。
外に出る機会が減ったことによる運動不足や生活リズムの乱れ、そしてコミュニケーションの不足や孤独感などによるストレスが、メンタルヘルスの不調をきたす要因と考えられています。
ストレスが解消されない状態が続くと、仕事に影響を及ぼすこともあるでしょうし、さらにモチベーションを低下させることにも繋がりかねません。
このような悪循環を招くことのないよう、早い段階で何かしらの対策を取ることが望まれます。
▷テレワークうつの危険性とは?原因や症状の特徴・予防の対策法を解説
従業員へのテレワークにおける健康管理の問題
テレワークで目の前に従業員がいないことで見えづらい、健康面の問題ですが、主に下記の課題があげられます。
- 環境の変化によるストレスへの対処法がわからない
- 従業員の健康変化に気が付きにくい 家庭で労働環境を整えることが難しい
企業がこれらの課題を認識することで、何らかの対策を講じることは十分可能でしょう。それではここで、テレワークによる健康面の課題について、いくつかの例をご紹介します。
環境の変化によるストレスへの対処法がわからない
企業がテレワークを導入してまだ年月が経っていないことから、在宅で勤務する従業員へのストレスケアをどのようにすればよいのかわからないといった声も聞かれます。
企業として、何かしら手を打たなければならないことを理解しつつも、何ができるのかわからないといったジレンマを抱える担当者も少なくありません。
▷テレワークによるストレスの原因とは?ストレスを解消する方法も紹介!
従業員の健康変化に気が付きにくい
テレワークの場合、従業員が働く様子を確認できないので、健康の変化に気が付きにくいといった難点があります。
オフィス勤務の頃は対面でコミュニケーションを取ることができ、顔色や言動から、従業員の体調の変化を察知することができました。
ところがテレワークに移行すると、どうしても物理的なコミュニケーション不足が生じてしまいます。従業員によっては、顔色が悪くても「少し体調が悪いくらいで休んではいけない」と無理をして仕事をしてしまう人もいます。
オフィスで勤務していれば、周囲の人が気が付いて声をかけることもできますが、テレワークではそのようなことも不可能です。働く人の顔が見えないテレワークでは、従業員の健康を気遣うことがとても難しいといえるでしょう。
家庭で労働環境を整えるのは難しい
企業が、従業員の家庭での労働環境を整えることが難しいという課題もあります。家庭はプライベートな空間でもある一方で突如、仕事場にもなっているような状況です。
ネットワーク環境が整っていなかったり、Web会議中に子どもが走り回っていたりして集中できないといった声もよく聞かれます。
テレワーク環境を整えるための通信費・光熱費や、デスクワークのための机や椅子などの購入費を支給している企業もありますが、テレワーク環境の整備には企業の担当者も頭を悩ませていることでしょう。
▷テレワークにおすすめの場所は?自宅以外にも便利なスポットを紹介
テレワークの健康問題を解決する方法
テレワークによって従業員の健康面で問題が生じてしまうと、全体での業務効率が落ちてしまうため、早急な対処が必要となります。ここからは、テレワークの健康問題を解決するための方法について紹介していきます。
労働環境を整えるための福利厚生を作成する
テレワークではオフィスと違って仕事用の机や椅子がなく、日常生活で利用するダイニングテーブル・チェアやこたつなどで仕事をしているケースがあります。
仕事に適していない机や椅子に長時間仕事をしてしまうと、姿勢が悪くなってしまい、肩こりや腰痛につながるリスクがあります。
そのため、労働環境を整えるためにも福利厚生を整えて、会社側が机や椅子などの購入を負担するなどの制度を作成しましょう。会社が負担することによって、従業員に金銭的な負担をかけずに健康問題を解決することができます。
従業員の健康面について定期的なヒアリングをする
テレワーク中では健康に関する問題を従業員自身が発しなければならず、中には申告することを躊躇ってしまう従業員もいます。そのため、会社側で定期的に健康状況をヒアリングするような働きかけをしましょう。
「直近の体調はどうか」「体に異変はないか」などを会社からヒアリングすることによって、従業員の健康状況を把握でき、大きな問題になる前に対処を取ることができます。
健康情報の発信やオンラインセミナーの実施
企業はオンラインセミナーなどを活用し、従業員に向けた健康情報を発信しましょう。企業が情報を伝えることで、働く人のヘルスリテラシーを向上させることが、この活動の狙いです。
このような活動によって、従業員の健康管理意識を高め、大きな病気を発症したりストレスを抱えたりするリスクを軽減させることも可能でしょう。
健康管理アプリの導入
従業員に健康管理アプリを導入するようすすめることも一つの手です。健康管理アプリには、本人が気付きにくい体調の変化などを通知してくれるものもあります。
アプリには以下のようなものがあるので、従業員のヘルスケアを担当する人は知っておくとよいでしょう。
- 睡眠管理アプリ
- 運動習慣管理アプリ
- 体重管理アプリ
- 食生活管理アプリ
睡眠を取ることは健康の基本です。睡眠管理アプリには、体の動きから睡眠を分析できたり眠りの浅いタイミングで起こしてくれるアラームの付いたものもあります。
運動習慣アプリは、ウォーキングなどの距離や速度、平均心拍数を計測することが可能で、運動不足に陥ってないかを管理できます。
また、体重管理アプリでは、筋肉量や体脂肪を記録できるほか、食生活管理アプリにはカロリー計算ができたり、AIトレーナーが栄養分析やアドバイスをしてくれるものもあります。
アプリには無料で利用できるものも多く、それぞれ機能が異なるので、目的に合わせて導入を検討してみるのもよいでしょう。
オンラインによる産業医の相談会の創設
オンラインで産業医に相談できる機会を設けることも、効果が高い取り組みでしょう。オンラインの場合、人目を気にせず相談することも可能です。
上司には話しにくいことでも、社外の産業医になら話せるということもあるでしょう。こうした対応で、従業員のメンタルヘルス問題などの早期発見と適切な対応に繋げていくことができれば理想です。
▷テレワークで社員のモチベーションは低下する?原因と対策方法10選
▷テレワーク導入の際に就業規則の変更は必要か?手順や注意点を徹底解説
手軽にできるテレワーク中の健康への働きかけ
テレワーク中に健康を維持するには、常に健康を意識しておいて毎日少しずつ働きかけをすることが重要です。ここからは、手軽にできる健康の促進方法について紹介していきます。
出勤前・退勤後に散歩する
テレワークでは通勤や退勤などで移動する上で歩く機会が少なくなってしまい、運動不足・気分転換ができなくなります。
そのため、出勤前や退勤後に時間を作って散歩する習慣をつけるようにしましょう。毎日20分程度の短い時間でも健康に良い影響があります。
また、散歩して太陽光を浴びることによって、リラックス効果・気分転換の効果も期待できるでしょう。
食事に気をつかう
テレワーク中はついついお菓子を食べたり、食事量が増えてしまったりと、食生活が乱れがちです。食生活の乱れは様々なリスクにつながるため、できるだけ健康を意識した食事を心がけましょう。
間食をしない・一汁一菜の食事を用意するなど、毎日の食事が健康な生活につながります。
企業が健康管理に活用すべきケアについて
企業が働く人の健康管理を行う際は、心と体の両方をケアする必要があります。とはいえ、具体的にどのように行えばよいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
ここからは、企業が活用できる従業員の疲労度チェックリストや、健康課題対策ができるアプリについてご紹介します。
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」
働く人の健康を守るために、従業員一人ひとりにどの程度の疲労が蓄積しているかを確認する自己診断リストは、本人が自覚していない疲れも客観的に把握することができます。
チェックリストの作成方法がわからない場合は、厚生労働省が公開している「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を参考にしてください。このリストをベースに、自社独自のリストを作成してもよいでしょう。
ただし、個人情報でもあるこの結果の取り扱いは、厳格に行うことが大切です。他の従業員が閲覧できないようにするなど、セキュリティを強化した上で実施しましょう。
[出典:厚生労働省「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」]
メンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
「こころの耳」は、厚生労働省が展開しているメンタルヘルスのポータルサイトです。ここでは、企業で働くヘルスケアの担当者や従業員、そしてその家族に向けた情報発信と、相談窓口の紹介などがされています。
| 提供元 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 機能・特徴 | 相談窓口紹介 メンタルヘルスに関するコンテンツ Q&A |
| URL | 公式サイト |
こうしたコンテンツを通して、従業員が健康管理への意識を高めることができれば理想です。
また、コンテンツには各企業がどのようにヘルスケアに取り組んでいるかも紹介されています。他社の事例も参考にして、ヘルスケアに関する自社の取り組みにも繋げていきましょう。
健康維持のためのアプリ「オンド・ユー」
パナソニックホールディングス株式会社が提供している「オンド・ユー」は、個人の健康を管理する一般的なアプリとは異なり、家族や多数のメンバーの健康を管理できるアプリです。
| 提供元 | パナソニックホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 機能・特徴 | 体温・体調管理 予防接種記録管理 体調のグラフ化 |
| URL | 公式サイト |
一つのグループで最大100名まで管理できるこのアプリは、企業が部署やチームで利用するのに適したアプリといえるでしょう。このような無料のアプリを試験的に導入してみてもよいかもしれません。
働く人の健康管理ができるアプリの利用は、コロナ禍で業務が増加しているヘルスケア担当者の負担の軽減にも繋がるでしょう。
テレワークにおいて従業員の健康管理対策は重要
この記事では、テレワークにおいて企業が実施すべき従業員の健康管理について紹介しました。
オフィス勤務だけでなく、対面でのコミュニケーションを取ることが難しいテレワークにこそ、ヘルスケア対策は重要です。健康管理を行うことによって従業員のビジネスパフォーマンスが向上し、それは企業にも還元されるでしょう。
あなたの企業で健康管理対策を実施するときは、この記事でご紹介した対処法やアプリを、ぜひ活用してみてください。
▼ DX相談窓口 | 中小企業向けIT活用の案内 ▼
Chatwork DX相談窓口は、チャットツールをはじめとして、あらゆる場面でビジネスをデジタル化・効率化するサービスを紹介しています。国内にて多くの中小企業にご活用いただいているChatworkならではのDX推進に向けた支援が可能です。
完全無料で、DXアドバイザーがお客様の課題をヒアリング・ご提案をさせていただきますのでぜひお気軽にチェック・ご相談ください。
▼ テレワークに役立つおすすめサービス ▼
オンラインストレージ「セキュアSAMBA」
クラウドIP電話「MiiTel」
RPAツール「RoboTANGO」
タスク管理ツール「Jooto」
日程調整ツール「調整アポ」
マニュアル作成ツール「COCOMITE」
▼ 一緒に読まれているおすすめ記事 ▼
テレワークの記事をもっと読む
-
ご相談・ご質問は下記ボタンのフォームからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
 ログイン
ログイン