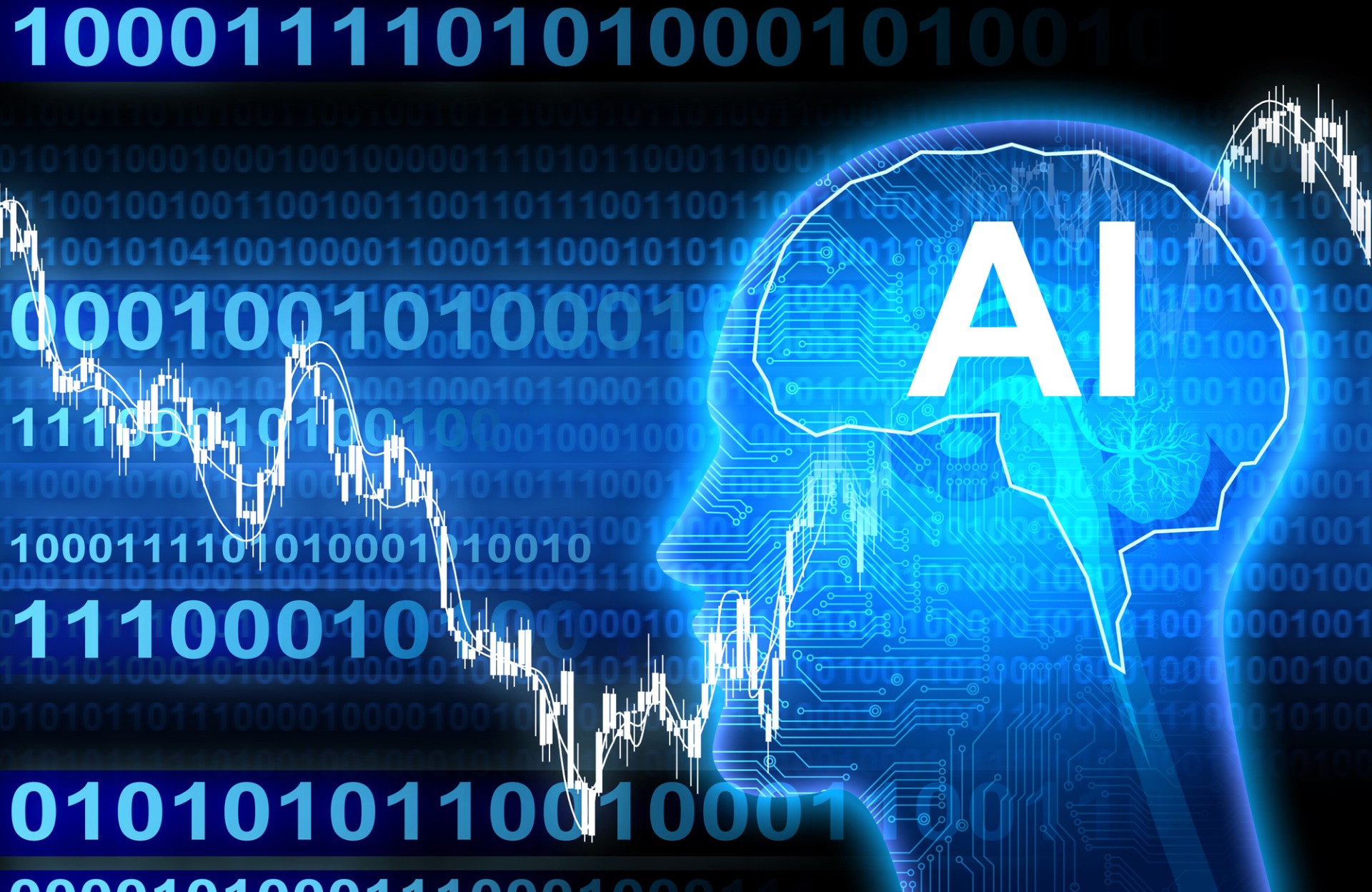モダナイゼーションとは?意味や具体的な手法・マイグレーションの違いについて解説

昨今、DXの重要性や推進が話題になる中で「IT用語のモダナイゼーションとは何か?」「マイグレーションとの違いが知りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。本記事ではモダナイゼーションの意味、マイグレーションとの違い、DXに不可欠な理由についても解説します。

監修者 福本大一 株式会社kubellパートナー アシスタント事業本部|ユニット長 大学卒業後、toC領域のWEBメディア事業で起業。事業グロースに向けたSEO戦略から営業・運用広告に従事し、約2年間の経営を経て事業譲渡。2021年3月からChatwork株式会社(現:株式会社kubell)に入社し、カスタマーマーケティングやアライアンスを経験した後、メディア事業・運用広告事業の責任者としてミッションを遂行する。現在は、DXソリューション推進部のマネージャーとして新規事業領域のセールス・マーケティング・アライアンス・メディア事業を統括。
目次
モダナイゼーションとは?
モダナイゼーションとは、老朽化した既存システムを今後のニーズに併せて最新のものに刷新することです。簡単に言えば、いまだにWindows 95で仕事をしていたとして、それを最新のバージョンに置き換えよう、といったことを指します。
システムはアップデートしていかなければ老朽化していきます。システムは必ずしも単独で完結するわけではなく、通信システムや大元のOSなどと連携しているので、それらの更新に対応しなければ使えなくなっていきます。
しかし、ただのシステムアップデートとはニュアンスが異なります。昨今、システム周りはITを使ったビジネスの変革、すなわちDXの方向に向けて大きく変化しつつあります。この大きな流れの中で、ビジネス変革を見越したシステム更新を行っていくことがモダナイゼーションです。
▷DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義・重要性をわかりやすく解説
モダナイゼーションとマイグレーションの違い
マイグレーション(Migration)の直訳は「移行、移動、移住」といった言葉です。IT用語でマイグレーションを使う場合も、あるシステムから別のシステムに移行することを指しています。
マイグレーションには時系列の方向性はありません。つまり、最新のシステムに進もうが古いシステムに進もうが、移行すればマイグレーションです。モダナイゼーションが「方向性」だとすると、マイグレーションは「動作」と言えます。
モダナイゼーションはビジネス変革を見越して今まで使っていなかった機能や新しい考え方などが加えられたり、不要なものが削られたりするかもしれません。一方、マイグレーションは従来のシステムの機能をそのまま新しいシステムで動かせるように、まさに「移行」することです。
ビジネスでは一般的にレガシーマイグレーションのことを指しています。「レガシー」とは過去の資産といったニュアンスであり、古く時代遅れといった意味を含みます。
例えば、昔のOSで動かしていたシステムを、その内容はそのままに、新しいOSでも動かせるようにする、といったことがレガシーマイグレーションです。
DXとの違いについて
DXとモダナイゼーションの違いは、DXは事業のあり方・戦略の変革、モダナイゼーションはシステムの刷新ということです。
DXとは、デジタル化とそのデータ活用によって新たな価値を創出することを目的とするビジネス変革そのものです。その過程には、ビジネスのプロセスで生じる情報をデジタル化する「デジタイゼーション」それらをシステム化する「デジタライゼーション」があり、それらを更にビジネスモデルの変革につなげることが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
モダナイゼーションは、その過程の中では既存のシステムをDXが推進しやすい形に刷新することを指します。昔から事業活動のデータをとり、KPIとしてモニタリングしているという例は多いと思います。
しかし、そのデータを集めるシステム自体が大昔に作られたもので、もはやウイルス対策などのフォローも行われていなかったり、データが他のシステムと連携できない形式だったりする場合があります。これらを解消し、時勢に合った形式に移行することをモダナイゼーションと呼びます。
▷DX戦略とは?成長に欠かせない理由や成功へ導く戦略の立て方を徹底解説!
▷デジタイゼーション・デジタライゼーションとは?違いやDXとの関係を解説
DXにモダナイゼーションが不可欠な理由
経済産業省のDXレポートによると、アンケート調査した8割以上の企業で、会社の基幹システムは構築されて既に何年もたっているなど、旧来のIT環境の上に成り立つシステムに依存している状況であることが分かりました。
しかし非常に近い将来、その前提である「旧来のIT環境」が変化しようとしています。この変化が避けられない状況であるため、モダナイゼーションは不可欠と言われています。
レガシーシステムと2025年の崖
2025年の崖とは、2018年の経済産業省のレポートで提議された問題であり、以下のように記されています。
あらゆる産業において、新たなデジタル技術を活用して新しいビジネス・モデルを創出し、柔軟に改変できる状態を実現することが求められている。しかし、何を如何になすべきかの見極めに苦労するとともに、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムも足かせとなっている。複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合、2025 年までに予想される IT 人材の引退やサポート終了等によるリスクの高まり等に伴う経済損失は、2025 年以降、最大12兆円/年(現在の約3倍)にのぼる可能性がある。
[出典:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」]
これまでPCの普及に伴い、多くの会社でオリジナルの社内イントラ整備やシステムのカスタマイズが行われ、次第にカスタマイズされていき、場合によってはM&Aなどにより他社のシステムも一部使いつつ新たなシステムを作り、複雑化が進んでいます。
こうした昔ながらのシステム(=レガシーシステム)は、その上でビジネスが回っているだけに、変更しにくい現実があります。しかし、2025年までに、現在日本の企業で使われている様々なOSやシステム(Windows 10、固定電話網、SAP ERP等)でサポートが終了し、今の仕組みが使えなくなる日は間近に迫っています。
世界はDXの方向へどんどん変化し続けており、いち早く大量のデータを獲得・利用しながらゲームチェンジを狙うという状況になっています。このままでは多くの日本企業はデジタル競争時代に勝ち抜くことができず、その損失額は2025年以降、最大で年間12兆円に昇ると見積もられているのです。これを「2025年の崖」と呼んでいます。
したがって、ビジネスを継続するには最低でもサポートが修了するシステムについてはモダナイゼーションが必須だと言えます。その際、複雑化・ブラックボックス化したシステムをそのままマイグレーションするのではなく、データを活用していくかといった発想の元でシステムを設計すると、DXにもつながっていくと考えられます。
▷レガシーシステムとは?DX推進を阻む原因や放置するリスクについて
▷2025年の崖とは?経産省のレポートの要点やDX推進のシナリオについて
DXのためにモダナイゼーションをするメリット
モダナイゼーションはブラックボックスと化したシステムから脱却し、時勢に合ったより一般的な形式に変更していくことですから、少なくとも以下の2点のメリットが生じます。
セキュリティの安全性向上につながる
ウイルス対策やシステムサポートが継続されるため、情報漏洩やデータの破壊といったリスクを軽減することができます。
IT技術の普及によってウイルスやサーバー攻撃などのセキュリティリスクが高まっており、従来のシステムを使い続けると様々なセキュリティリスクが発生します。
その中でモダナイゼーションでシステムを最新の状態に更新していけば、セキュリティリスクを防ぐことができます。自社のセキュリティを向上できる点がモダナイゼーションの大きなメリットです。
業務効率の向上につながる
従来のレガシーシステムを使い続けることによって、データ処理速度が遅い・機能が少ないなどの問題が発生し、業務効率が低い状態から抜け出せなくなります。
そこでモダナイゼーションを進めることにより、データ処理速度が早い・機能が豊富などのシステムに刷新できるので業務効率の向上にもつながります。これまでにデジタル化できなかった業務にも対応してくれるので様々な面で恩恵が受けられます。
▷DX化とIT化の違いとは?必要性やDXを推進する方法をわかりやすく簡単に解説
モダナイゼーションの3つの方法
モダナイゼーションを実行する方法としては、一般的にリプレース、リライト、リホストといった3つの方法があり、それらを行うにあたってリファクター、リドキュメントの2つが必要な準備となっています。
1.リプレース
リプレースとは、既存のシステムやそれを動かすための機器を従来のものとは全く別物にして、新しくシステムを立ち上げることを指します。
リプレースのメリット
新しいシステムを立ち上げるので、複雑化・ブラックボックス化した過去のシステムといった負の遺産を一掃できます。また、今後の戦略との整合性が取れた設計にすれば、業務の効率化だけでなく、競争力の成長加速やDXの実現といったことも期待できます。
リプレースのデメリット
新たに立ち上げるとなると、全社的なシステムの見直しが必要になったり、細かく業務の見直しを行ったりする必要があり、莫大なコストと手間が想定されます。戦略が定まっていなければ、余計な投資にもなりかねません。
2.リライト
リライトとは、既存のシステム内容・仕様はそのままに、プログラムの言語などを別のものに置き換える手法のことです。従来のレガシーシステムの機能や仕様を活かしつつ、新しい機能を追加するイメージです。
リライトのメリット
既存のシステムを活用できるので、リプレースよりもコスト・手間がかかりません。システムの仕様に大きな変化がないので、使い手が不都合を感じることも少ないと考えられます。
リライトのデメリット
別の言語に置き換える際に、既存のシステムがどのような設計になっているか、全て洗い出さなければならず比較的難易度が高い手法です。
部署ごとのカスタマイズなどにより複雑化している場合や、前任者の退職などにより設計内容が継承されていない場合は、再現が困難となる可能性があります。
3.リホスト
リホストとは、一般的に、ミドルウェア(エミュレーションソフトウェア)を利用して既存のシステムをそのまま移行する方法です。エミュレーターによってパソコン上でゲーム機のファミコンやプレイステーションのソフトを動かすことができるように、新しいシステム環境で旧来のシステムを動かすことは可能です。
なお、エミュレーションでどうしても一部の機能を再現できないような場合もあり、その際は新しいシステム上のソフトウェアでその差分を補うプログラムを追加することになります(コンバージョン)。
リホストのメリット
リホスト(つまりエミュレーション)には、旧来のシステムに通じたスタッフが不在でメンテナンスのしようもなかったシステムであっても再現できるというメリットがあります。
既存のシステムがそのまま使えるイメージであり、使い手にとって最も混乱が少なく、手間もコストも抑えることができます。他のシステムとの連携が少ない独立したシステムには有効な方法のひとつです。
リホストのデメリット
過去のシステムを継続使用することになるので、例えばブラックボックス状態は相変わらず解決されないといった事が生じます。また、あくまで仮想上の運転であり、他のシステムとの連携には不向きです。
モダナイゼーションを実施する上での事前準備
これまでに紹介したモダナイゼーションを進める上で必要な事前準備について紹介していきます。
リファクター
システムのプログラムは、機能の追加など様々な仕様変更を経て次第に複雑化していきます。複雑化したプログラムにはもはや重複や削除してよい部分もあります。
現行システムで使っている機能はそのままに、どのような仕組みになっているのか、その設計を整理しプログラムをすっきり(最適化)させることをリファクターと呼びます。
この過程で、機能全体の棚卸を行い、移行させる部分と削除する部分を明確にしていきます。
リドキュメント
システムの設計情報を可視化し、文書などに整理することをリドキュメントと言います。可視化していれば、どの部分をどのようなスケジュールで移行させるか、どの部分に問題があって改善が必要か、どの部分を作り直すか、といったことが検討しやすくなります。
▷DX推進は3段階のフェーズがある?各プロセスの定義や進め方について
モダナイゼーションを進める手順を解説
モダナイゼーションを遂行する手順としては、まず体制を作り、現状分析を行い、戦略と照らし合わせながら対象を決め、導入するシステムを検討します。
このとき、前提として整理されていなければならないのは、「3C」と「7S」です。
3Cは、顧客(Customer)競合(Competitor)自社(Company)のことです。外部環境がどのように変化し、それに対して自社の状態がどのようになっているか、という情報の整理です。
7Sとは、経営資源について整理するためのフレームワークです。会社の共通の価値観(Shared value)を中心に、戦略(Strategy)組織構造(Structure)システム(System)会社の持つ技術(Skill)スタッフ(Staff)経営スタイル(Style)といった要素があります。
システムが7Sを見たときにバランスの取れているものでなければなりません。7Sは全てが完璧に整っていることではなく、それぞれが関連しあってバランスが取れていることが重要です。
例えば、ラフな説明ですが「スタッフの人数は少ないけれど、あるシステムを使って不足を補える」「優秀な人材を確保するため世界レベルのテレワークを戦略の中心にしている。
その結果、組織構造は緩くせざるを得ないが、あるシステムで円滑なコミュニケーションとナレッジの蓄積を実現している」など、整合性を考える必要があります。
まずはこれらによって、DXという観点で自社が目指すべき方向をある程度決めます。そのうえで、以下のステップをとります。
1.予算や人員などの念入りな計画を立てる
モダナイゼーションは単にシステムをバージョンアップすればよいのではなく、先々を見据えたリソースの投入になります。計画性を持って臨まなければなりません。
計画を立てるため、まずは現状把握から始めます。現状把握はまずIT資産のおおまかな棚卸からです。リストアップのほか、サポート期限など緊急対応の必要性なども整理します。
IT資産のリストができたら、自社の立ち位置とひとまずのゴールを決めます。このプロジェクトによってどの状態(現状)からどの状態(ゴール)に移行したいのか、明確にしておきます。
自社の立ち位置を客観視するにあたっては、経済産業省が定めるDX認定制度の「DX推進指標」を利用するのも有効でしょう。
ここまでの時点で、いつまでに何をやるか、ある程度課題が明らかになっていると思います。経営陣からプロジェクト進行の承認を得ておきます。
以上の要領で人を巻き込む準備ができたら、プロジェクトのメンバーを決めます。ある部署にとって大切なIT資産が、このプロジェクトによって抹消されていたという事件のないよう、メンバー選定にはご注意ください。
▷DX推進の鍵となるアジャイル型組織とは?重要な理由やメリットについて
▷DX推進には不可欠なビジョンとロードマップ策定の重要性について
2.現行のIT資産を細かく分析
IT資産をより細かく分析していきます。システムのサポート期限切れが迫り、今後安全に使うことが困難であるものや戦略の肝となるものを優先しましょう。既存システムの中に、既に使われていないアプリケーションや機能はないか、確認します。
ここは非常に重要で、使っていないものまでマイグレーションすると不要なコストが発生することになります。また、逆に移行漏れにより必要な機能が使えなくなったということのないようにしなければなりません。
次に、目的に応じた新しいシステム基盤を選択します。これまでの分析を基に、どの部分を移行させるか、既存システムと互換性があり移行がスムーズかを検討し、金額と期間の見積もりを立てます。
以上の過程で、リファクターやリドキュメントを行います。移行の検討には、システムに使われている言語や使われているコード、データベース構造などを確認する必要があるので、スキルを持った人材が必要となります。社内のリソースで対応が困難であれば、外注も視野に入れましょう。
3.自社のメインシステムをしっかりと確認
新しいシステムへの移行後、社内全体のシステムに不具合が出ないかチェックを行います。例えば、データベースを新しいものに移行した場合は、データの保管方法が変わることにより様々なシステムに影響が出る可能性があります。検証のステップは、単独での動作確認後、他のシステムと連結させた上での動作確認を行います。
新しいシステムが他のメインシステムとも並存できる事が確認出来たら、旧システムを凍結させます。移行にあたってどのようなトラブルが発生しそうか十分想定の上、移行期間を設定し社内にアナウンスします。
▷DX推進にシステムの内製化は必要?メリット・デメリットや進め方を解説
▷DX戦略とは?成長に欠かせない理由や成功へ導く戦略の立て方を徹底解説!
▼ DX相談窓口 | 中小企業向けIT活用の案内 ▼
Chatwork DX相談窓口は、チャットツールをはじめとして、あらゆる場面でビジネスを効率化するサービスを紹介しています。国内にて多くの中小企業にご活用いただいているChatworkならではのDX推進に向けた支援が可能です。
完全無料で、DXアドバイザーがお客様の課題をヒアリング・ご提案をさせていただきますのでぜひお気軽にチェック・ご相談ください。
モダナイゼーションを成功させる秘訣
モダナイゼーションを成功させるための秘訣について紹介していきます。失敗しないためにもどのような点を注意すれば良いのかチェックしておきましょう。
現状のシステムや体制を把握しておく
モダナイゼーションを成功させるためには、企業で使われているシステムやツール、社内の体制を把握することが大切です。現状を理解することによって、課題が明確になり何から始めれば良いのかが優先順位をつけられます。
把握してどの領域でモダナイゼーションが必要なのかを明確にすることによって、全体ではなく局所的にスモールスタートで始めることが可能です。
また、モダナイゼーションに向けた最適なアプローチ方法が見つかるため、滞りなくスムーズな移行が実現します。
社内の人員を巻き込む
モダナイゼーションを推進する上ではできるだけ実際にシステムを利用している現場のメンバーも巻き込んで進めていきましょう。現場が感じている課題感と相違があるとモダナイゼーションの意味合いが薄くなってしまいます。
また、推進している中でのテスト段階で現場のメンバーがいることによって、ニーズに応じた対処ができて効率的に進みます。導入後の不満やトラブルのリスクも低くなるのでなるべく周りの社員を巻き込むようにしましょう。
モダナイゼーションの失敗事例
ここからはモダナイゼーションに失敗した事例について紹介していきます。自社のモダナイゼーションに失敗しないためにも、失敗事例をチェックして対策しておきましょう。
逆にコストがかかったしまった
一般的に、モダナイゼーションにかかった費用は減価償却費としてコストに反映されます。既に使わなくなったシステムや成長のドライバーとして役立たないものまで移行対象にすると、単純にコストアップするという結果に陥りがちです。
コストが膨らみすぎないようにするには、あらかじめ発生するコストを詳細に洗い出して何にいくらくらいの予算が発生するのかを明確にしておくことが大切です。
リサーチ不足で想定通りに進まなかった
社内のシステムは、様々な「例外事象」や「個別案件」に対応するという形で構造が複雑になってしまったものがあるかもしれません。こうしたものを紐解かずに移行しようとすると、データの変換がうまくいかなかったり、今までできていたサービスができなくなったりすることが想定されます。
現状の紐解きが不十分のまま外注してしまうと、ベンダーに丸投げの状態になりかねません。そしてベンダーも複雑な構造のシステムを完全に解読することは困難であり、結果的に想定以上の時間とコストを費やすことになったり、必要な機能が再現できなくなるといったトラブルが発生しがちです。
また、あれもこれもと盛り込んだり過度な費用対効果を狙ったりすると、計画に無理が生じて頓挫することがあります。その上、実際の効果は思ったほどではなかったということもあり得ます。
▷注目すべき海外のDX推進事例15選!事例からみる日本との比較も解説
▷DXの成功事例15選!先進企業から学ぶDX推進を成功させるポイント
モダナイゼーションを外部に依頼する方法
これまで説明してきたように、モダナイゼーションは自社のリソースだけでは困難であることが多いと思います。何もかも自前でやるよりも、アウトソーシングしたほうが良い場合もあります。
外部委託するには、まず委託先を探さなければなりません。検索エンジンで「地域名、システム、ベンダー」といったキーワード検索を行えば、お近くのベンダーを見つけることは可能です。
また、自社にマッチする開発会社を選定してくれるサービスも存在しています。どういった会社を選ぶべきかわからない場合は、まずサポートしてくれるサービス会社に問い合わせてみるといいでしょう。
▷DXコンサルティングとは?必要な企業や導入メリット・選び方を解説
適切なモダナイゼーションを実行してDX推進へ
モダナイゼーションはシステムの棚卸、システムを介する業務の分解、戦略との整合、時勢に合った形への移行といった事を全て含む、非常に大きなテーマです。しかも、実行しなければ多くの企業で今後事業継続の危機や業務の混乱にも直面する可能性を抱えています。
しかし、逆に捉えればこの困難を乗り切れば、業界内で優位を築くチャンスでもあります。事業戦略とテクノロジーへの感度を兼ね備えた人材をチームに入れて、モダナイゼーションを遂行し、DXへの道を拓きましょう。
▷DXフレームワークとは?経済産業省が提唱する内容をわかりやすく解説
▷DXとUX・CXとの違いとは?関連性や混同しやすい類義語も解説
▼ DX相談窓口 | 中小企業向けIT活用の案内 ▼
Chatwork DX相談窓口は、チャットツールをはじめとして、あらゆる場面でビジネスを効率化するサービスを紹介しています。国内にて多くの中小企業にご活用いただいているChatworkならではのDX推進に向けた支援が可能です。
完全無料で、DXアドバイザーがお客様の課題をヒアリング・ご提案をさせていただきますのでぜひお気軽にチェック・ご相談ください。
DXの記事をもっと読む
-
ご相談・ご質問は下記ボタンのフォームからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
 ログイン
ログイン